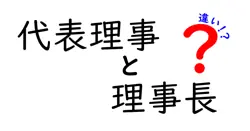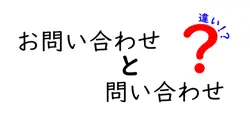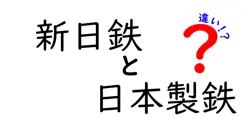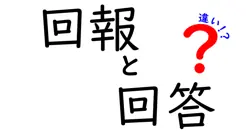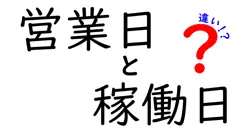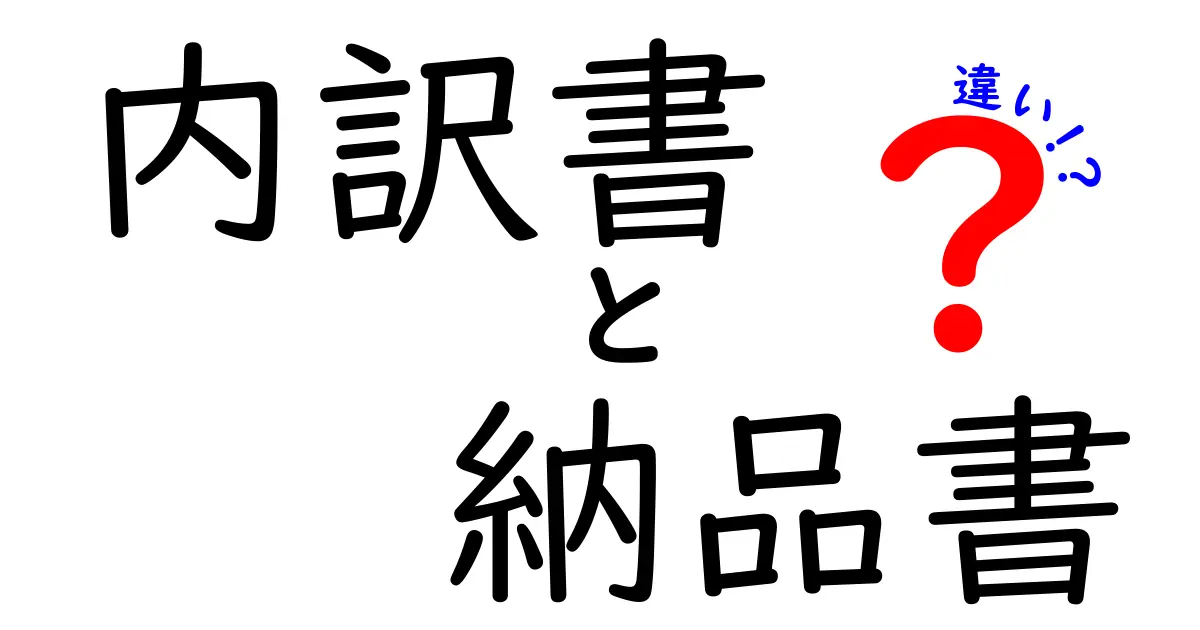
内訳書と納品書の違いを徹底解説!ビジネスシーンでの役割とは?
ビジネスの現場では、さまざまな書類が作成されます。その中でも「内訳書」と「納品書」という書類は、特に重要な役割を果たしています。しかし、これらの書類がどう違うのかを理解している人は少ないかもしれません。今回は、内訳書と納品書の違いについて、わかりやすく解説します。
内訳書とは?
内訳書は、発注に対する詳細な内容を説明するための書類です。たとえば、製品やサービスの項目を一覧にし、それぞれの単価や数量を記載します。内訳書は発注の際の確認書類として使われ、発注者と納入者の両方が内容を確認することが目的です。
納品書とは?
一方、納品書は実際に商品が納入された時に発行される書類です。納品書には、納品された商品の明細や数量、発送日などが記載されています。納品書は受領書としても使われることが多く、受け取った側はこれを使って商品の内容を確認します。
| 項目 | 内訳書 | 納品書 |
|---|---|---|
| 目的 | 発注詳細の確認 | 商品受領の証明 |
| 発行タイミング | 発注時 | 納品時 |
| 主な内容 | 項目、単価、数量 | 納品された商品明細、数量、日付 |
内訳書と納品書の使い分け
内訳書と納品書は、それぞれ別のタイミングで使われるため、混同しないようにしましょう。内訳書は発注の際に必要ですが、納品書は商品を受け取った後に必要です。ビジネスの中でどちらの書類も重要な役割を担っていますので、正しく理解して活用しましょう。
まとめ
内訳書と納品書の違いを理解することで、ビジネスシーンでのミスを防ぐことができます。正しい知識を持って、スムーズな業務を行いましょう。
内訳書という言葉を聞くと、ビジネスシーンでの「詳細を記載した書類」というイメージが強いですが、実はその使い方には少し面白いエピソードがあります
例えば、ある企業では内訳書を作成する際に、デザイナーが細かいアートワークを追加して、発注書を見せることで取引先との信頼関係を深めようとしたとか
こうした工夫は、ただの契約書に命を吹き込むことができるんですね
内訳書は、堅苦しいだけの文書ではなく、コミュニケーションツールとしての側面もあるんです
前の記事: « 内訳書と明細書の違いを徹底解説!あなたに合った書類を選ぶために