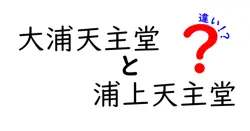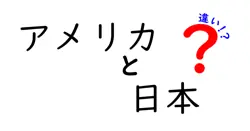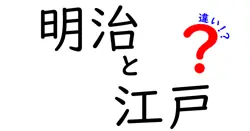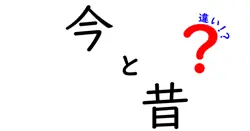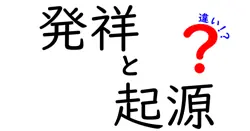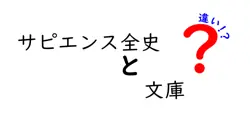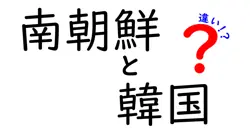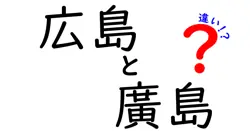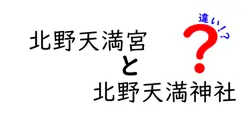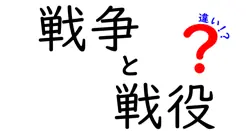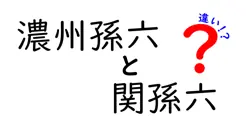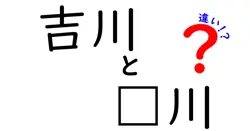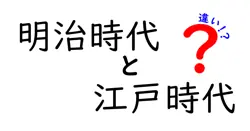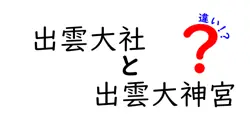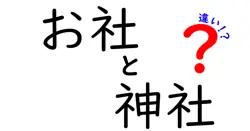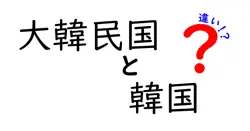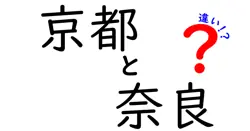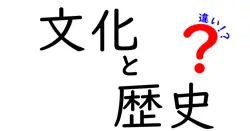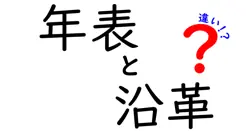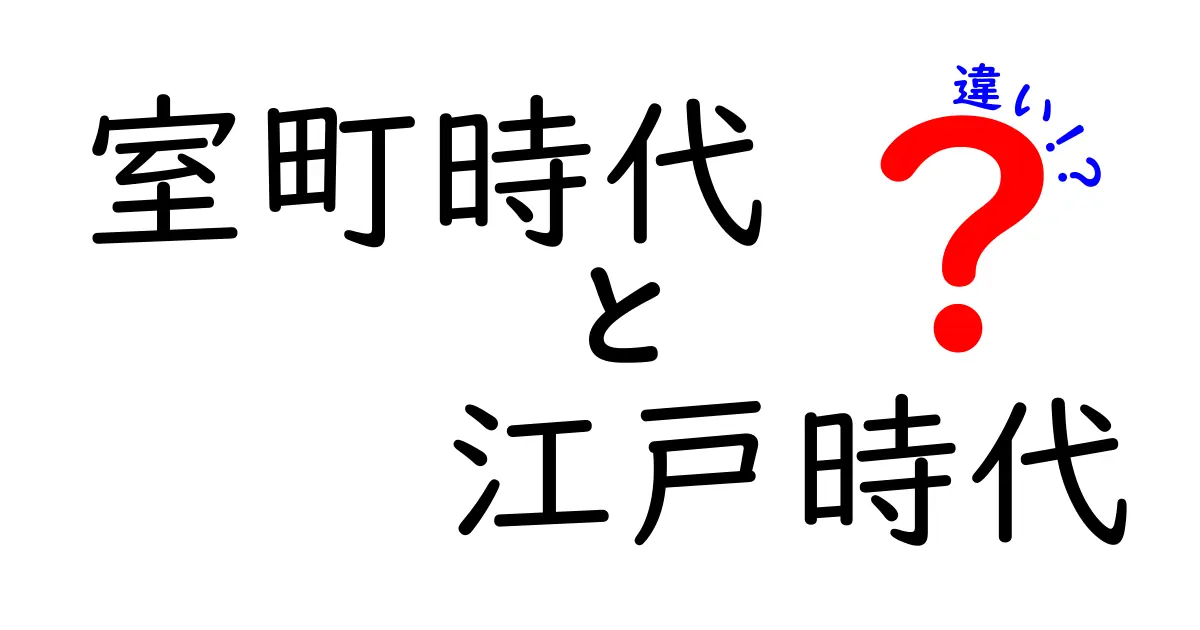
室町時代と江戸時代の違いを分かりやすく解説!
日本の歴史には、室町時代(1336年〜1573年)と江戸時代(1603年〜1868年)という二つの重要な時代があります。この二つの時代は、政治や文化、社会の面で多くの違いがあります。そこで、今回の記事では、室町時代と江戸時代の違いについて詳しく解説していきます。
1. 政治体制の違い
室町時代は、足利氏が幕府を開き、武士が政治を行っていました。この時代は、中央集権的な体制がまだ確立されておらず、武士たちの力が強く、地方分権的な状態でした。一方、江戸時代は徳川家康が幕府を開き、約260年間にわたって平和な時代を実現しました。江戸時代では、中央集権的な政治が確立し、身分制度も厳格に設けられました。
2. 文化の違い
室町時代は、茶道や能、また水墨画などの文化が栄えました。この時代は、戦乱が続く中で武士たちが文化を愛した結果、特に武士階級の文化が育まれました。江戸時代になると、浮世絵や歌舞伎、町人文化が発展し、多くの人々が楽しめる芸術が生まれました。
3. 社会の違い
室町時代は、士農工商の身分制度が緩やかであり、戦国時代には多くの人が自由に移動しやすい状況がありました。それに対して、江戸時代は厳格な身分制度が存在し、町人や農民は自由に動けなくなってしまいました。このように、社会の構造も大きく変わりました。
4. 経済の違い
室町時代は、一部の大名が自分の領地で商業活動を行い、商人が発展しました。江戸時代に入ると、徳川幕府が平和な時代をもたらし、商業が発展します。特に、江戸や大阪といった大都市が栄え、多くの商人が成長しました。江戸時代は、商業や都市文化が大きく発展した時代でもあります。
まとめ
室町時代と江戸時代は、それぞれ異なる特徴や背景を持っていました。政治体制、文化、社会、経済の面での違いを理解することで、日本の歴史をより深く知ることができます。
| 要素 | 室町時代 | 江戸時代 |
|---|---|---|
| 政治体制 | 武士による地方分権 | 中央集権的な幕府 |
| 文化 | 茶道、能、水墨画 | 浮世絵、歌舞伎、町人文化 |
| 社会 | 士農工商の緩やかな制度 | 厳格な身分制度 |
| 経済 | 大名による商業活動 | 商業の発展と大都市の栄え |
室町時代と江戸時代の違いを知ると、日本の歴史をより楽しめますよね
特に江戸時代は、商人や町人が発展し、文化が花開いた時代です
例えば、浮世絵は今でも多くの人に愛されていて、日本の伝統的なアートの一つとして世界中に知られています
室町時代の茶道も、今に続く重要な文化の一部です
これらの文化は、当時の人々の生活や価値観を反映していて、お互いに影響を与え合ってきました
前の記事: « 大阪市と大阪府の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 東京と青森の違いを徹底解説!あなたはどちらが好き? »