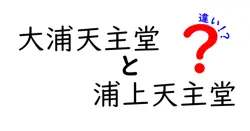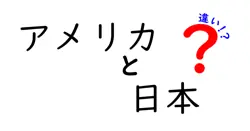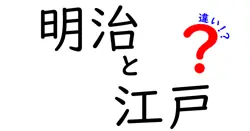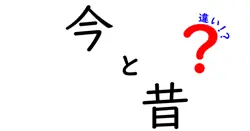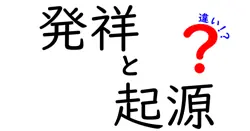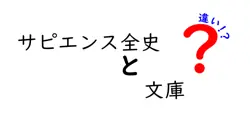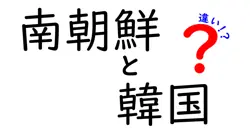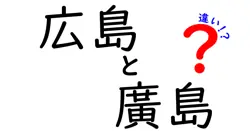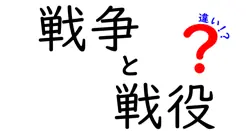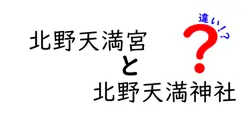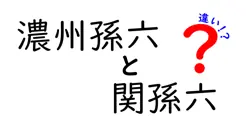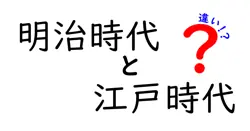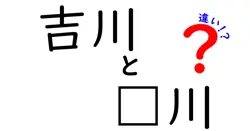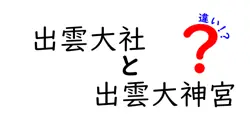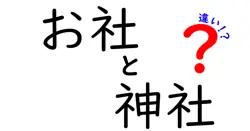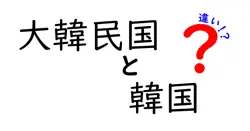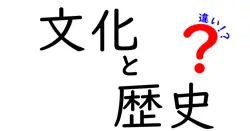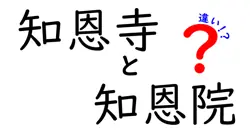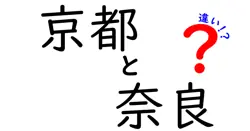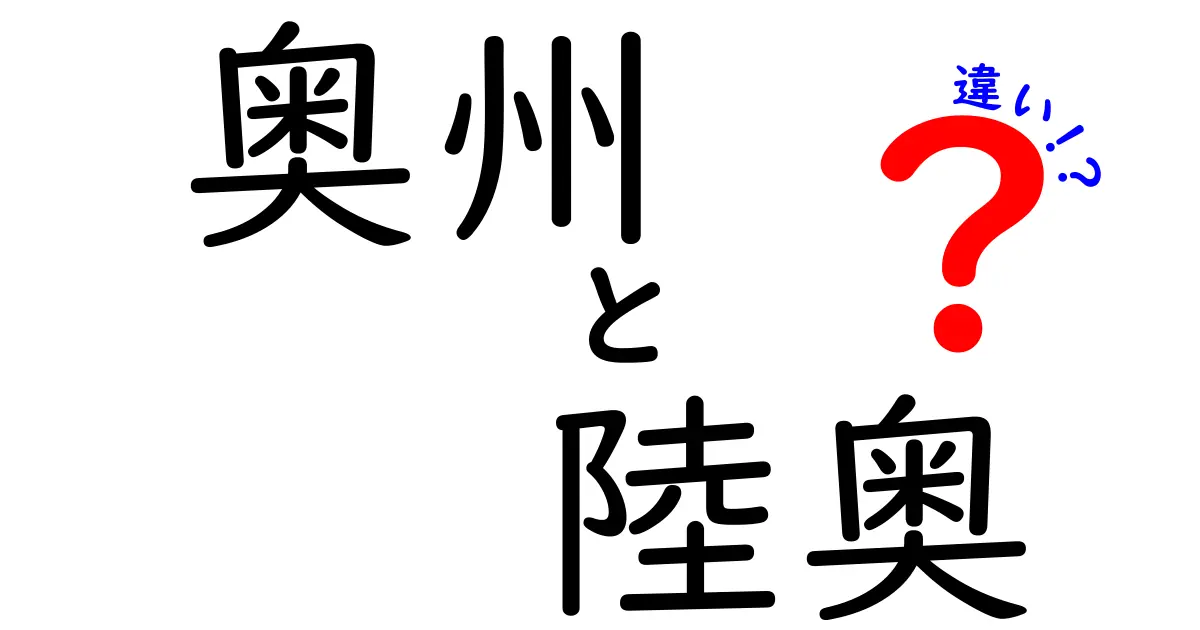
奥州と陸奥の違いとは?歴史や地理から見えてくる真実
日本にはさまざまな地域名がありますが、特に「奥州」と「陸奥」という言葉は、古くからある名称であり、しばしば混同されがちです。両者は似た響きを持つため、どちらも東北地方と関連があることは確かですが、実際には異なる意味を持つ言葉です。
奥州とは
「奥州」は、古代から中世にかけて使用された地域名で、主に現在の東北地方の一部、特に仙台などを含む地域を指します。歴史的には、平安時代の武士の活躍や、江戸時代の藩制度において重要な役割を果たしました。
陸奥とは
「陸奥」は、主に青森県と岩手県を含む地域を指しますが、場合によっては現在の「陸奥国」として、青森県、岩手県、秋田県の一部をも指すことがあります。特に奈良時代から続く国名であり、陸奥は日本の重要な地域の一つとされています。
奥州と陸奥の違い
| 観点 | 奥州 | 陸奥 |
|---|---|---|
| 地域 | 主に宮城県の仙台周辺 | 青森県、岩手県を中心とした地域 |
| 歴史的背景 | 平安から江戸時代にかけての武士文化 | 奈良時代から続く古い国名 |
| 現在の利用 | 観光地や歴史的なエリアの名前として使われる | 地域名や行政区画名として利用される |
このように、「奥州」と「陸奥」は、地理的にも歴史的にも異なる意味を持つ言葉です。それぞれの地域は独自の文化や歴史を有しており、訪れる価値がある場所です。
ピックアップ解説
奥州と陸奥、どちらも日本の歴史に深く関わっていますが、特に陸奥という名称は、古くからの国名として重要な意味を持っています
また、陸奥は「おく」とも呼ばれ、特に陸上交通の要所としても知られています
実際、平安時代の古文書でも「陸奥」という用語は多く見られ、当時の人々がこの地域をどれほど重視していたかがわかりますね
前の記事: « 公認陸上競技場とは?一般の陸上競技場との違いを徹底解説!
次の記事: 民芸と民藝の違いとは?知って得する日本の伝統文化 »