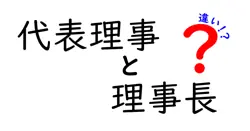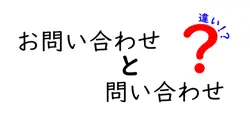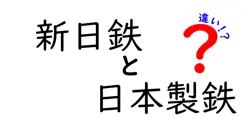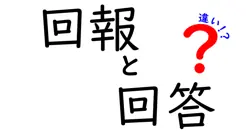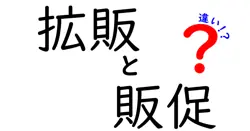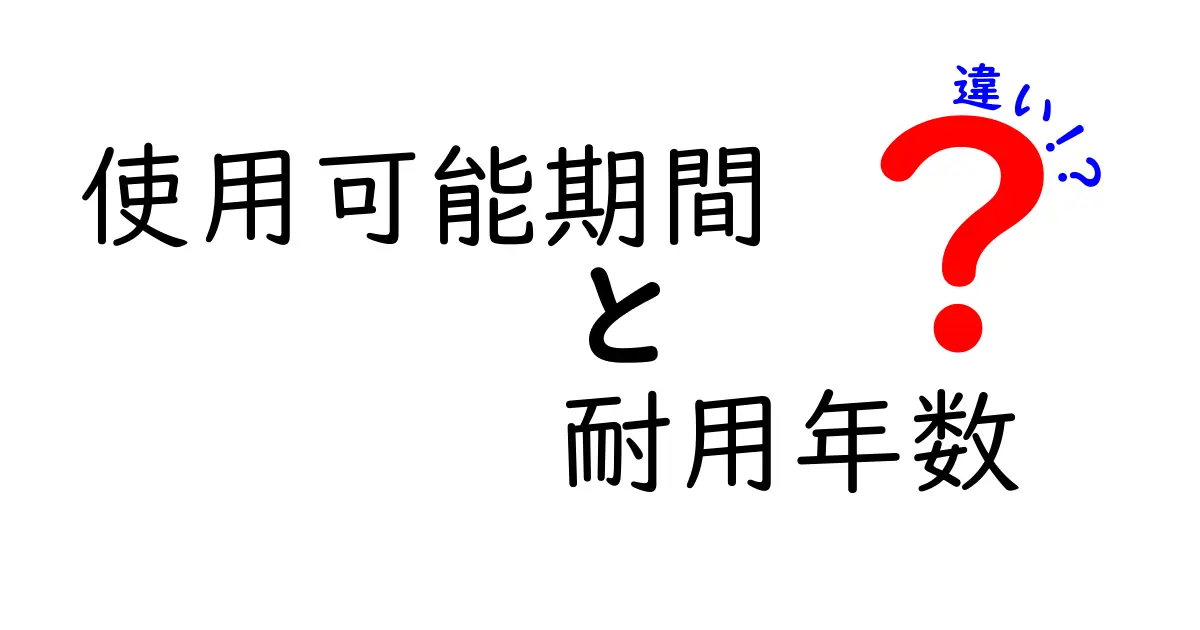
使用可能期間と耐用年数の違いをわかりやすく解説!
私たちが生活している中で、さまざまな商品やサービスがありますが、それぞれには「使用可能期間」と「耐用年数」という言葉が使われています。この二つの言葉は似ているようで、異なる意味を持っています。この記事では、その違いについて詳しく解説します。
使用可能期間とは?
使用可能期間とは、製品やサービスが正常に使用できる期間のことを指します。例えば、食品や医薬品には消費期限や使用期限が設けられており、その期間内に消費することが推奨されています。また、電池や電子機器なども使用可能期間があり、その期間が過ぎると性能が劣化してきます。
耐用年数とは?
一方、耐用年数とは、物品がその価値を維持できる期間のことを言います。耐用年数が設定されている物品は、会計上の減価償却の計算において重要な役割を果たします。例えば、会社が購入した設備は、耐用年数を基にして価値が減少すると考えられます。この耐用年数は、法令や規則に基づいて定められることが一般的です。
使用可能期間と耐用年数の違い
| 項目 | 使用可能期間 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 定義 | 製品が正常に使用できる期間 | 物品の価値を維持できる期間 |
| 関連商品 | 食品、医薬品、電池など | 設備、建物、車両など |
| 目的 | 安全に使用するため | 資産管理のため |
まとめ
以上のように、「使用可能期間」と「耐用年数」は異なる意味を持っています。同じように見えるかもしれませんが、それぞれの言葉が用いられる場面は異なるため、正しい理解が必要です。特に消費者として、使用可能期間は安全に利用するために知っておくべき大切な情報です。また、ビジネスにおいては耐用年数を理解することが、資産管理や会計業務において重要になってきます。これからは、これらの違いを意識して生活していきましょう!
使用可能期間という言葉、実は食品や医薬品にしばしば使われますが、消費期限や賞味期限との関連が深いです
消費期限はその食品が安全に食べられる最後の日を示し、賞味期限はその味や栄養が最も良い状態を保てる期間を示します
びん詰めのジャムなんかは、賞味期限が切れてもすぐには悪くないことが多いですが、食べる時は自己判断が必要
使用可能期間は製品の性能を理解する手助けにもなるので、しっかり確認したいですね!
次の記事: 償却年数と耐用年数の違いを徹底解説!わかりやすく学ぼう »