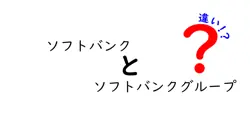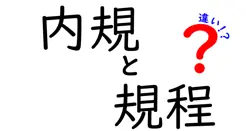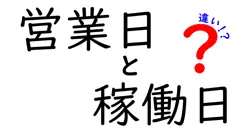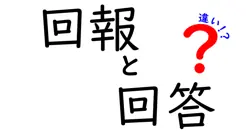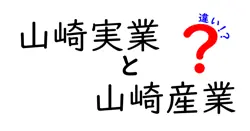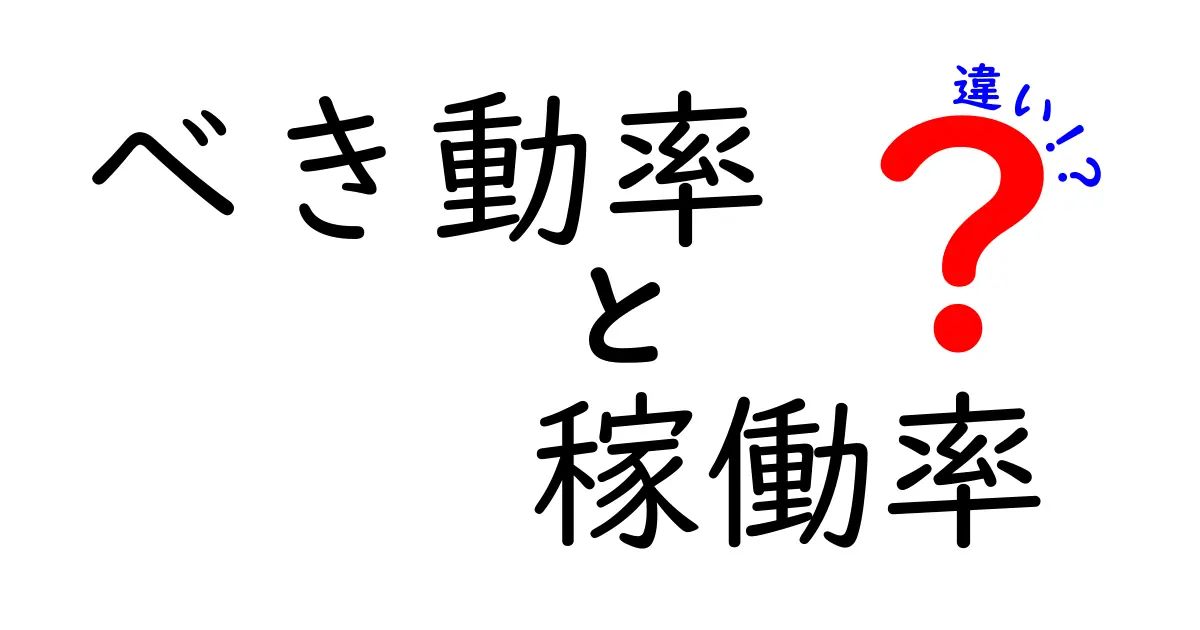
べき動率と稼働率の違いを徹底解説!分かりやすく比較してみよう
最近では、工場や製造業で「べき動率」や「稼働率」という言葉を耳にする機会が増えています。これらの言葉は、効率や生産性を測る上で非常に重要ですが、意味が似ているため混同されがちです。今回はこれらの違いについて解説します。
べき動率とは?
べき動率は、一定期間における生成可能な生産量に対して、実際に生産された量の割合を示します。具体的には、理論上の生産能力が100%とした場合に、実際の生産量がどれだけあるかを示す指標です。たとえば、ある工場が1日に100個の製品を製造できるとした場合、実際に80個の製品を製造したら、べき動率は80%になります。
稼働率とは?
稼働率は、使用可能な時間のうち実際に機械や設備が稼働している時間の割合を示します。この指標は、例えば、機械が24時間稼働可能な状態の中で、実際にどれだけの時間稼働したかを測ります。もし、24時間中16時間しか稼働していなければ、稼働率は66.67%となります。
べき動率と稼働率の違い
| 指標 | 定義 | 計算方法 |
|---|---|---|
| べき動率 | 理論上の生産可能量に対する実際の生産量の割合 | 実際の生産量 ÷ 理論的な生産量 × 100 |
| 稼働率 | 使用可能な時間に対する実際の稼働時間の割合 | 実際の稼働時間 ÷ 使用可能な時間 × 100 |
たとえばこんな場合
あなたが友達とお菓子作りをすることを考えてみましょう。レシピでは1時間で10個のお菓子を作れると書いてあり、実際には30分で6個作ったとします。この場合、べき動率は60%ですが、もし実際に使った時間が1時間だったとすると、稼働率は50%ですね。
まとめ
べき動率と稼働率は似ているようで、実は異なる概念です。べき動率は生産の実績評価を示し、稼働率は設備の利用効率を示します。これらを正しく理解することで、効率的な生産活動が行えるようになるでしょう。
べき動率って、一見難しそうに見えますが、実は日常的なことに使われているかもしれません
たとえば、学校の勉強でも同じような考え方ができますよ
テストでの点数を、得点の最大点で割って100を掛ければ、実際の勉強の効果が分かります
勉強をもっと効率よく進めたいと考えると、べき動率が高い=良い結果、ということが見えてきますね!
前の記事: « OEEと稼働率の違いとは?工場の効率を考える
次の記事: 可動率と稼働率の違いとは?わかりやすく解説! »