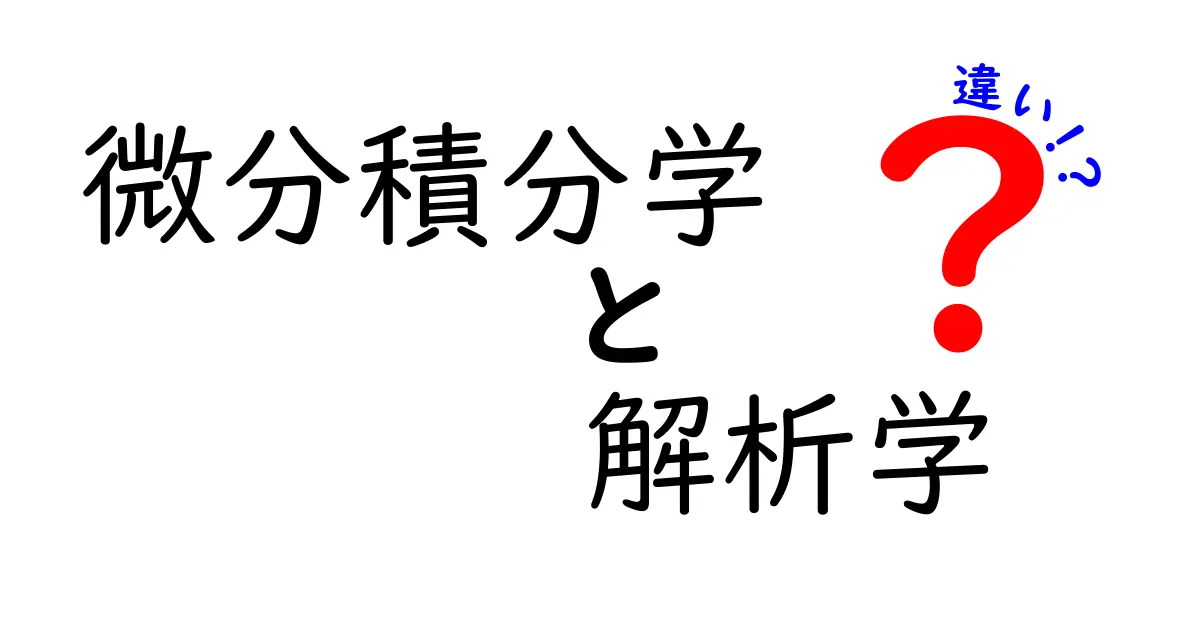
微分積分学と解析学の違いをわかりやすく解説!
数学の世界にはさまざまな分野があり、微分積分学と解析学はその中でもとても重要な二つの分野です。両者の違いについて、今回はわかりやすく解説していきます。
微分積分学とは?
微分積分学は、主に関数の変化を扱う分野です。「微分」は関数の瞬時の変化率を求める方法であり、「積分」は関数の面積や総和を求める方法です。たとえば、車のスピードを考えたとき、スピードが変化する速さを求めるのが微分です。一方、ある時間の間に走った距離を求めるのが積分になります。
微分と積分の例
| 考える対象 | 微分 | 積分 |
|---|---|---|
| 車のスピード | 瞬間的なスピードの変化 | 特定の時間に走った距離 |
解析学とは?
解析学は、関数の性質やその挙動をより深く探求するための数学的手法を研究する分野です。微分積分学が基本的な計算手法を学ぶのに対して、解析学では限界や連続性、収束など、より高度な概念が出てきます。解析学は、大局的な視点から数学を理解しようとする試みでもあるのです。
解析学の主なテーマ
- 関数の連続性
- 極限の概念
- 無限級数の収束
微分積分学と解析学の違い
このように、微分積分学は数学の基本的な計算手法を学ぶ分野であり、解析学はそれを用いてより深く探求するための分野だと言えます。つまり、微分積分学は実用的な技術を身につけるためのもので、解析学はそれを理論として確立させるためのものだということです。
まとめ
微分積分学と解析学は密接に関連していますが、学ぶ内容や目的は異なります。数学を学ぶ上で、両者の違いを理解することで、より深く数学を楽しむことができるでしょう。
微分積分学の「微分」は、言葉の意味として「小さな変化」という意味があります
この「微分」が登場するのは、例えば経済学の分野でもよく見られます
企業がどのくらいの利益を上げるかを計算するとき、売上の増加が変化する瞬間的な rate というものを求めるのです
この様な考え方は、ビジネスの世界でも非常に役立つのですよ!
前の記事: « 単項式と項の違いを徹底解説!中学生でもわかる数学の基本





















