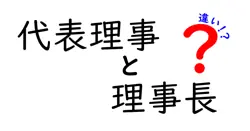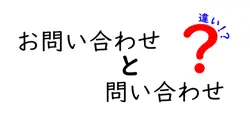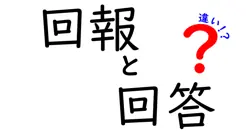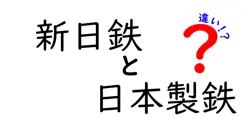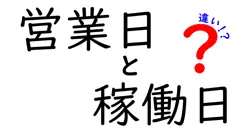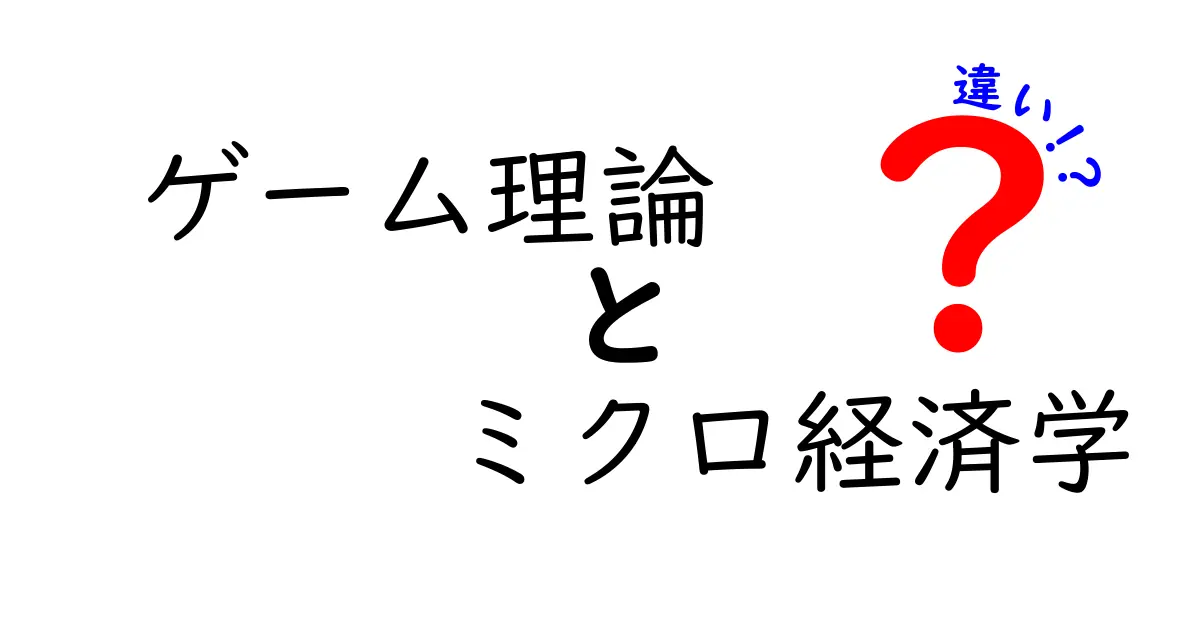
ゲーム理論とミクロ経済学の違いを徹底解説!
ゲーム理論とミクロ経済学は、経済学の中で非常に重要な概念ですが、それぞれの目的とアプローチに違いがあります。今回は、それぞれの特徴や関係性を分かりやすく紹介します。
ゲーム理論とは?
ゲーム理論は、複数のプレイヤーが関与する状況における戦略的意思決定を分析する学問です。プレイヤーはそれぞれの利益を最大化するために行動するため、他のプレイヤーの選択も考慮に入れなければなりません。たとえば、囚人のジレンマという有名な例では、2人の囚人が互いに裏切るか協力するかを選ぶことで、最終的な結果が変わります。
ミクロ経済学とは?
ミクロ経済学は、個別の市場や企業、消費者の行動を分析し、どのように資源が配分されるかを考える学問です。主に、需要と供給、価格決定、消費者選好などに焦点を当てています。ミクロ経済学では、消費者がどのように意思決定を行い、企業がどのように生産と販売を行うかなどを詳細に分析します。
ゲーム理論とミクロ経済学の違い
| 特徴 | ゲーム理論 | ミクロ経済学 |
|---|---|---|
| アプローチ | 戦略的意思決定 | 市場の動向分析 |
| 対象 | 複数のプレイヤーとその選択 | 個々の企業や消費者 |
| 目的 | 利益を最大化 | 資源の最適配分 |
| 使用する理論 | 均衡理論、戦略行動 | 需要供給理論、効用理論 |
まとめ
ゲーム理論はプレイヤー間の戦略的な関係を分析する一方で、ミクロ経済学は個別の市場や消費者、企業の行動に焦点を当てます。両者は異なる視点を持ちながらも、経済での意思決定において非常に重要な役割を果たしています。
ゲーム理論は時に、他人の行動を予測しながら自らの選択を考える必要があります
この考え方は、友達とのゲームでも実際に役立つことがありますよ!たとえば、相手がどんな戦略を考えているかを推測し、自分の行動を決める時などに使えるのです
それが、「自分だけではなく、他人の選択も意識しなければならない」というゲーム理論の本質です
時にはそれが、スポーツや日常の人間関係にまで役立つかもしれませんね!
前の記事: « ゲーム理論と心理学の違いを知らずに損していませんか?
次の記事: ゲーム理論と行動経済学の違いをわかりやすく解説! »