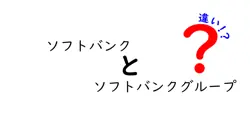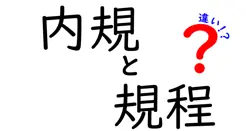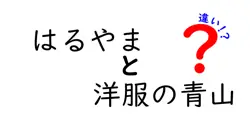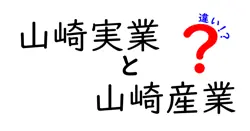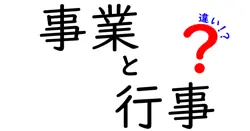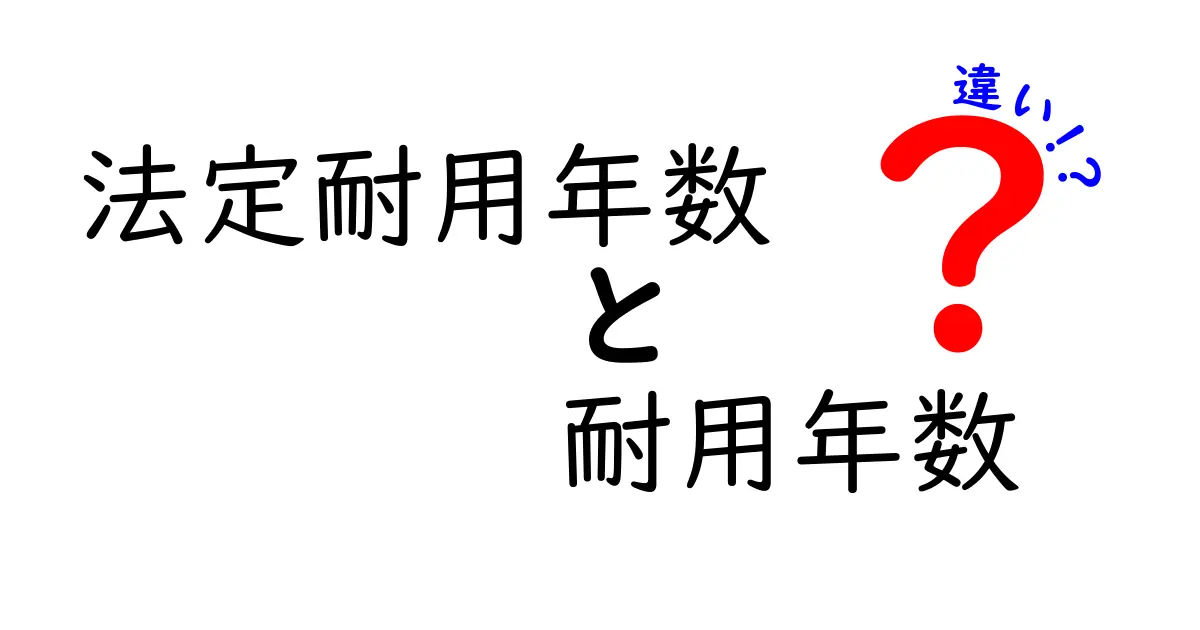
法定耐用年数と耐用年数の違いとは?わかりやすく解説!
私たちが日常生活で使用する物や建物は、時間が経つにつれて価値が減少していきます。そのため、物や建物の価値を正しく理解するためには「耐用年数」という考え方が重要です。
まず「耐用年数」とは、物を使用することができる期間のことを指します。たとえば、パソコンや自動車、家具など、それぞれの使用に適した期間が存在します。この期間が過ぎると、物はもう使えない、または大幅に性能が落ちてしまうと考えられています。
これに対して「法定耐用年数」というのは、税法上で定められた耐用年数のことを言います。つまり、国や地方自治体が、税金を計算する際に用いる特定の耐用年数です。この法定耐用年数に従うことで、企業は設備投資の税金を適正に計上することができます。
| 項目 | 耐用年数 | 法定耐用年数 |
|---|---|---|
| 定義 | 使用可能な期間 | 税法で定められた期間 |
| 対象 | 家庭用品や車両など全般 | 固定資産(建物、機械など) |
| 計算方法 | 使用状況による | 税法に基づく |
耐用年数は使い方や条件にもよるため、同じ物でも人によって異なる場合があります。しかし、法定耐用年数は国の法律で決まっているため、ほぼ一定です。また、法定耐用年数を正しく知っておくと、税金を計算する際に役立ちます。
このように、耐用年数と法定耐用年数は似ていますが、目的や使われる場面が異なると言えます。物の価値や資産管理を理解するために、この2つの違いを把握しておくと良いでしょう。
ピックアップ解説
法定耐用年数は税金計算の際に使われる特別な期間ですが、実際には物の使い方によってその寿命は変わることが多いです
例えば、家庭で使うパソコンは5年くらいと言われますが、仕事で毎日使っていたらその限りではないですね! 物の価値をしっかり理解することが大切です
前の記事: « 残存価額と簿価の違いを徹底解説!あなたの疑問をスッキリ解消
次の記事: 簿価と課税標準額の違いをわかりやすく解説! »