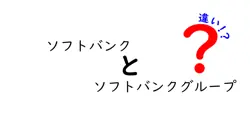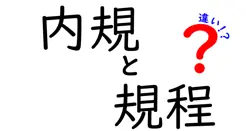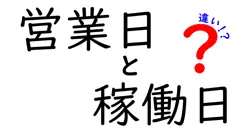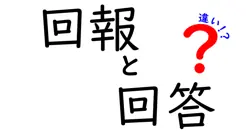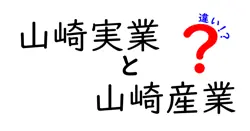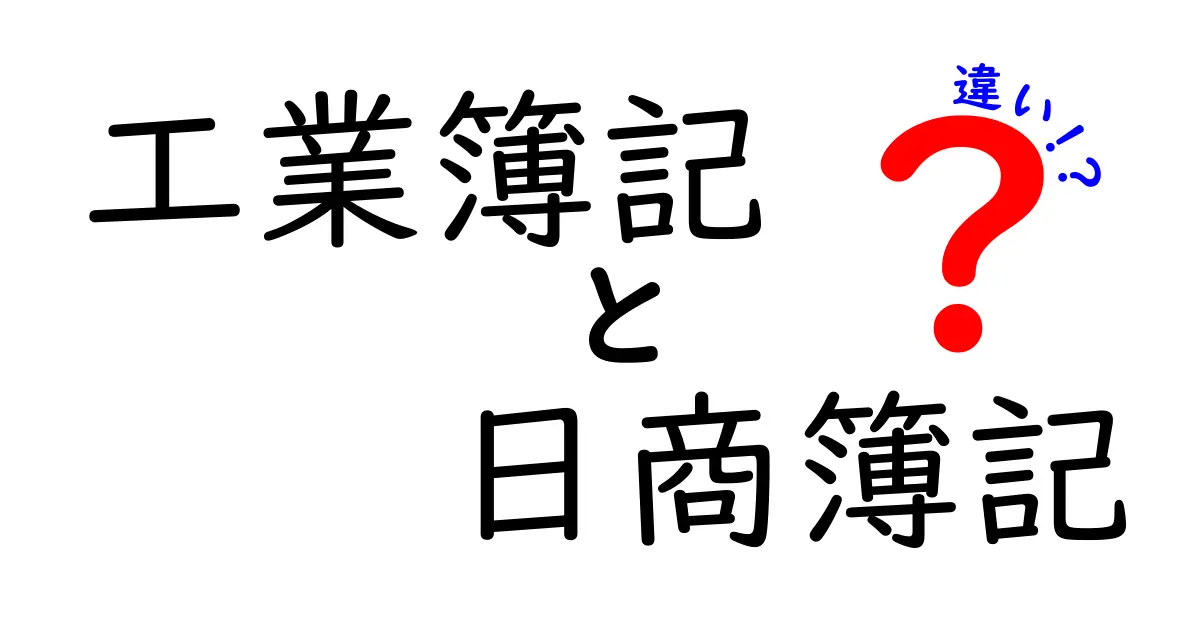
工業簿記と日商簿記の違いを徹底解説!どちらを学ぶべきか?
簿記を勉強し始めると、「工業簿記」と「日商簿記」という用語をよく耳にします。でも、これらは何が違うのでしょうか?今日は、中学生でもわかるように、工業簿記と日商簿記について分かりやすく説明していきます。
工業簿記とは
工業簿記は、主に製造業で使われる簿記の手法です。製品を作るためにかかった材料費や人件費、製造間接費などを細かく記録します。これにより、製品の原価計算ができ、企業が効率よく生産活動を行えるようになります。
日商簿記とは
日商簿記は、日本商工会議所が認定する資格で、主に一般的な商業簿記を学ぶものです。企業の財務諸表を作成するための基礎的な知識が含まれています。ここでは、売上や仕入れ、経費を管理し、利益を計算します。
工業簿記と日商簿記の主な違い
| 項目 | 工業簿記 | 日商簿記 |
|---|---|---|
| 用途 | 製造業 | 商業全般 |
| 対象 | 原価計算 | 財務諸表作成 |
| 計算内容 | 製品の製造コスト | 収益と費用の管理 |
このように、工業簿記は主に製品の原価を管理するためのものです。一方、日商簿記は企業全体のお金の流れを把握するために必要な知識を学びます。
どちらを学ぶべきか?
どちらを学ぶべきかは、将来の進路によります。例えば、製造業に就職したいと考えているなら工業簿記を学ぶことをお勧めしますし、商業やサービス業で働きたい場合は日商簿記を学ぶと良いでしょう。
それぞれの特性を知ることで、自分に合った簿記の勉強ができると思います。興味がある方は、ぜひ一歩踏み出してみてください!
工業簿記の原価計算は、単に製品のコストを把握するだけではありません
例えば、製品Aを作るのに必要な材料が10個、仕入れ値が1000円だとした場合、単純に10,000円となりますね
しかし、そこに工場の光熱費や人件費などの間接費を加え、製品の全体的なコストを正確に計算しないと、利益がどれだけ出るかは分かりません
こうした精密な計算ができると、経営者は戦略を立てやすくなります
だから、工業簿記は製品の価格設定にも大きく寄与するのです!
次の記事: 建設業簿記と日商簿記の違いを徹底解説!あなたに必要なのはどっち? »