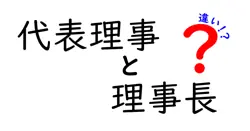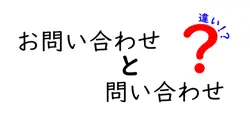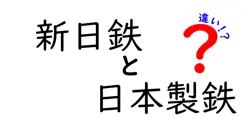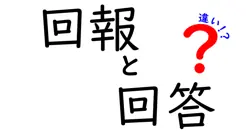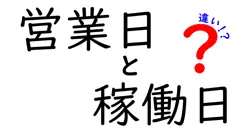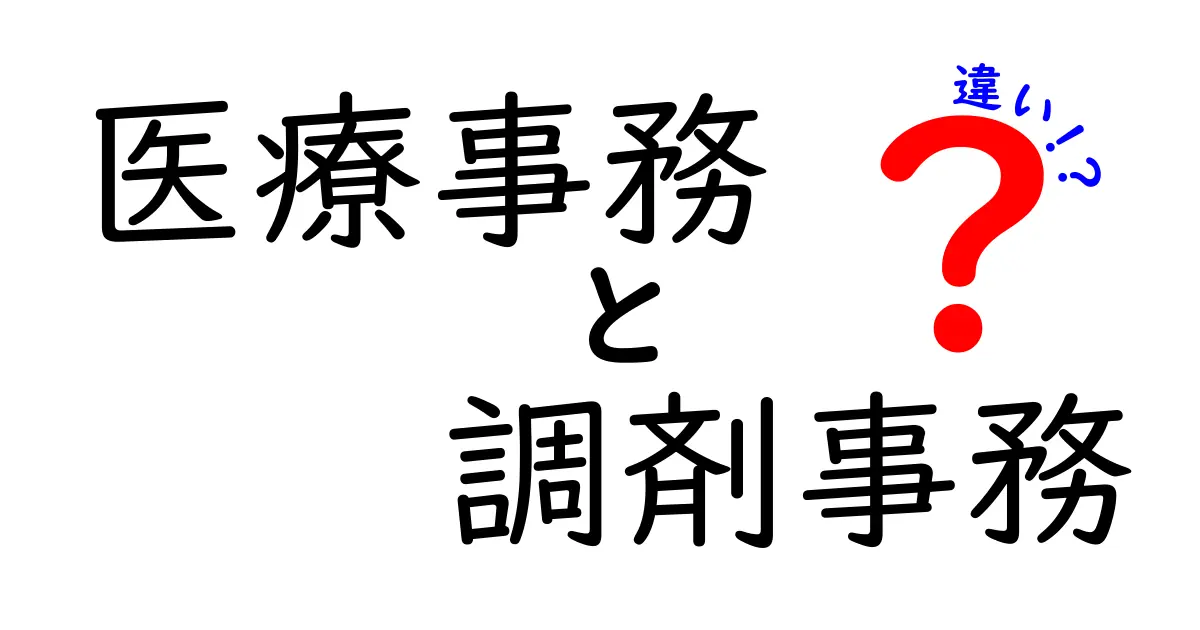
医療事務と調剤事務の違いとは?それぞれの役割をわかりやすく解説!
医療事務と調剤事務、似たような名称の職種ですが、実はその役割には大きな違いがあります。この記事では、医療事務と調剤事務について、それぞれの仕事内容や役割の違いを詳しく解説していきます。
医療事務とは
医療事務は、病院やクリニックの受付業務を担当する職種です。患者さんが来院した際に、受付での対応や、保険請求の手続き、診療内容の記録などを行います。また、医療事務は患者さんの個人情報を管理したり、医療費の計算を行うなど、医療現場では欠かせない存在です。
調剤事務とは
一方、調剤事務は薬局で働く職種です。調剤事務の主な役割は、処方箋に基づいて薬を調剤(調合)することや、患者さんへの薬の説明、保険請求業務です。また、調剤事務は薬剤師と連携して、より良い医療サービスを提供するために働きます。
医療事務と調剤事務の主な違い
| 項目 | 医療事務 | 調剤事務 |
|---|---|---|
| 勤務場所 | 病院、クリニック | 薬局 |
| 主な業務内容 | 受付、保険請求、診療記録 | 薬の調剤、患者への薬の説明 |
| 必要な資格 | 医療事務関連資格(例:医療事務管理士) | 調剤事務関連資格(例:調剤事務管理士) |
まとめ
医療事務と調剤事務は、いずれも医療現場において重要な役割を果たしていますが、その仕事内容や勤務場所には明確な違いがあります。医療事務は医療機関での業務が中心であるのに対し、調剤事務は薬局での業務を行います。
それぞれの職種で求められるスキルや資格も異なるため、興味がある方はぜひ自分に合った道を選んでみてください。
ピックアップ解説
調剤事務と聞くと、薬を調整するだけの仕事と思いがちですが、結構多彩な業務が含まれています
例えば、患者さんに薬を渡す時に、実はその人のお薬履歴を確認しているんです
これ、意外と重要で、アレルギーや他の薬との相互作用を考慮するために必要なんですよ
つまり、調剤事務は単なる薬の管理だけでなく、患者さんの健康を守る大事なお仕事でもあるんですよね
次の記事: 医療秘書と診療情報管理士の違いをわかりやすく解説! »