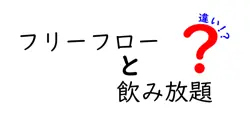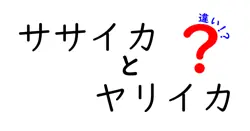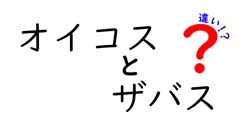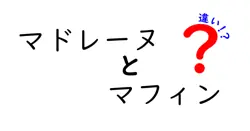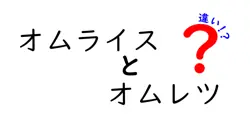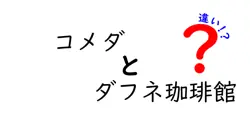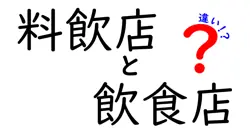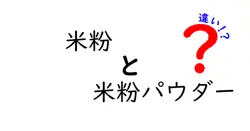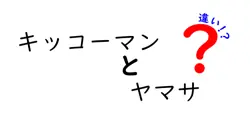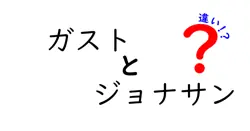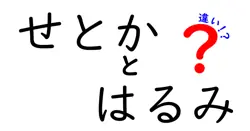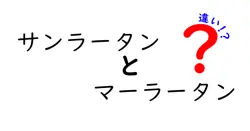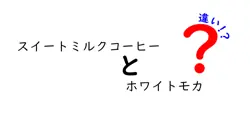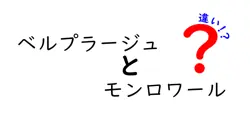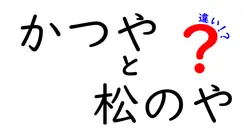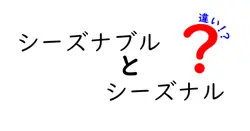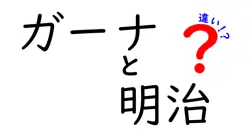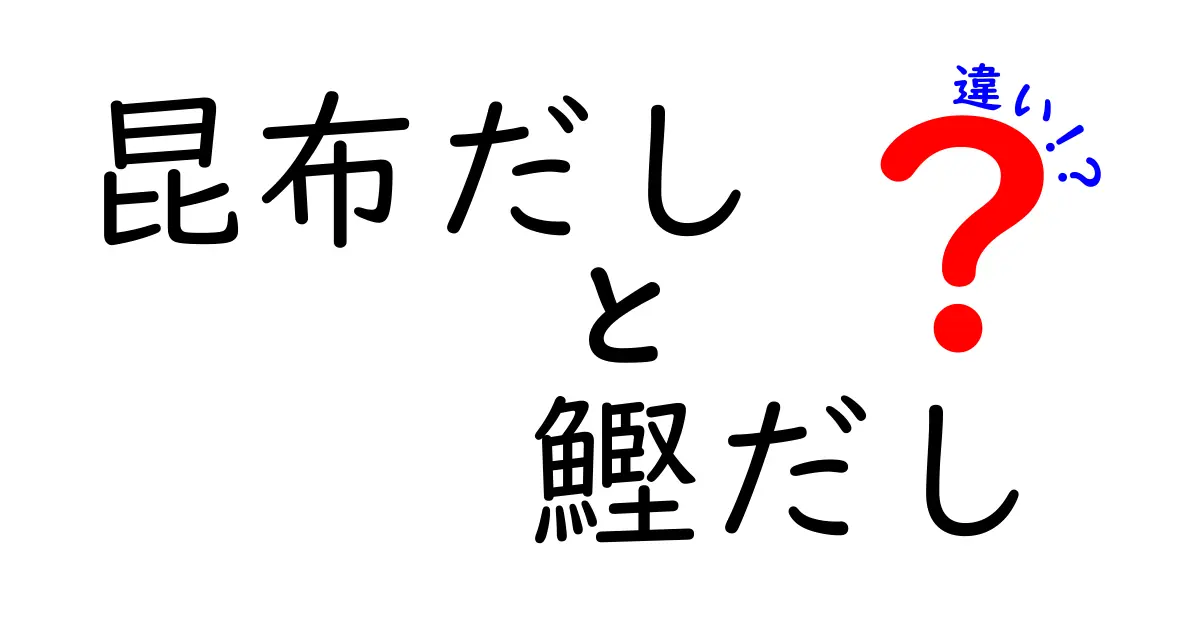
知っておきたい!昆布だしと鰹だしの違い
日本の料理に欠かせない「だし」。その中でも特に有名なのが昆布だしと鰹だしです。今回は、この二つのだしの違いについて詳しく解説します。
昆布だしとは?
昆布だしは、主に昆布という海藻から取れるだしです。昆布にはグルタミン酸が豊富に含まれていて、旨味成分が豊かです。昆布を水に浸して抽出することで、透明でやさしい味わいのだしが取れます。これは、主に味噌汁や煮物、お吸い物など和食全般に使われます。
鰹だしとは?
鰹だしは、鰹節から取れるだしです。鰹節は干した鰹を燻製にするなどの加工を施したもので、この加工によって香ばしさが増します。鰹だしは、昆布だしに比べて旨味成分のイノシン酸が豊かで、こくのある味になります。おそばやうどん、煮物、さらにはラーメンのスープとしても使われます。
素材の違い
| 項目 | 昆布だし | 鰹だし |
|---|---|---|
| 主な素材 | 昆布 | 鰹節 |
| 旨味成分 | グルタミン酸 | イノシン酸 |
| 特徴 | やさしい味 | こくのある味 |
使い分け方
昆布だしは、あっさりとした和食や繊細な味付けに適しています。一方、鰹だしはこくと香りが強く、特に濃い味の料理に向いています。両方を使い分けることで、旨味を引き立てた料理を作ることができます。
まとめ
昆布だしと鰹だしは、それぞれ異なる素材から作られ、旨味成分や味わいに違いがあります。両方のだしを使い分けて、日本の料理をより美味しく楽しみましょう!
昆布だしにはグルタミン酸が多く含まれていますが、ただの海藻と侮ってはいけません
実は、昆布が持つ旨味成分は、旨味を引き立てる重要な役割を果たしていて、だしだけでなく、様々な和食に不可欠な存在です
例えば、昆布を煮てもその旨味成分は残るので、煮物に使った後の昆布を細かく刻んで、他の料理に使うなんてこともできるんですよ
こうした工夫をすることで、無駄がなくて美味しい料理を作ることができます
前の記事: « 味噌汁と味噌鍋の違いを徹底解説!おいしさと楽しみ方の違いは?
次の記事: 生姜と金時生姜の違いを徹底解説!どちらが健康に良い? »