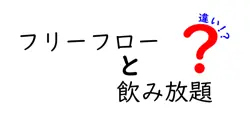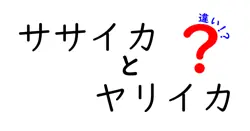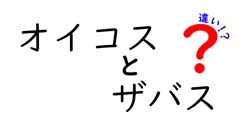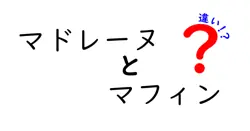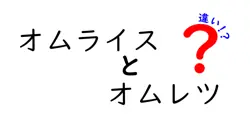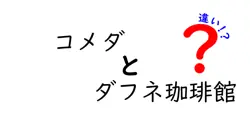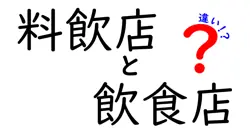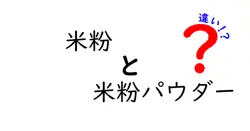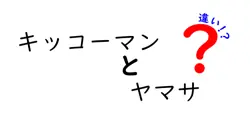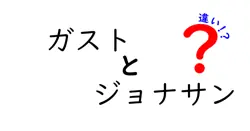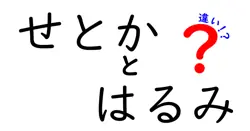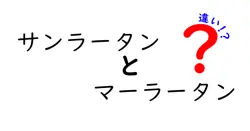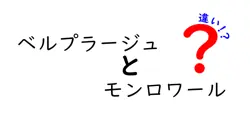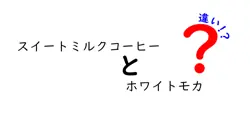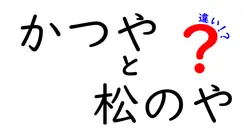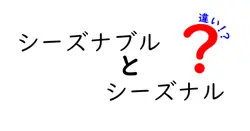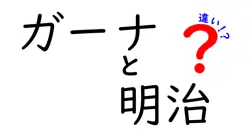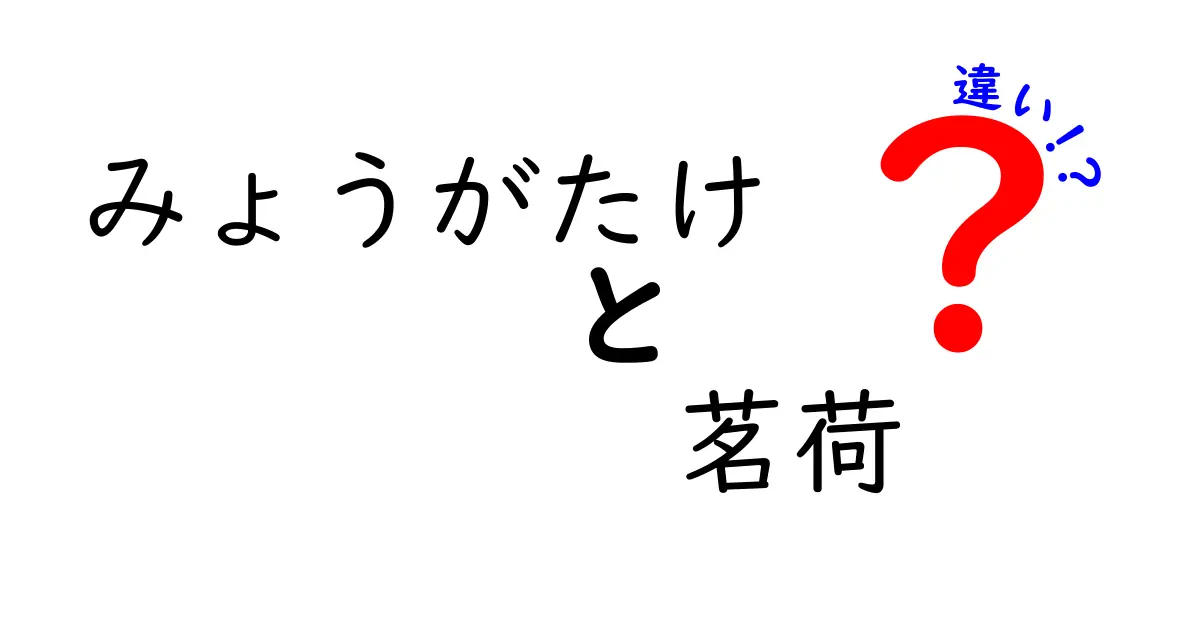
みょうがたけと茗荷の違いとは?その特徴と活用法
みょうがたけと茗荷は、どちらも日本の食文化に欠かせない植物ですが、その違いについては意外と知られていないことがあります。この記事では、みょうがたけと茗荷の違いや特徴を詳しく解説していきます。
みょうがたけとは?
みょうがたけは、主に日本や中国に自生するショウガ科の植物です。学名は Zingiber mioga で、特徴的な成長形態を持っており、通常は30センチメートルから1メートルほどの高さに成長します。葉は幅広く、立ち上がるように生えています。
茗荷とは?
茗荷(みょうが)は、同じくショウガ科の植物ですが、学名は Zingiber mioga で、みょうがたけとは異なり、食用部分として主にそのつぼみ(花茎)が利用されます。茗荷は、日本では特に夏の季節に食べられることが多く、独特の香りと風味が特徴です。
みょうがたけと茗荷の主な違い
| 項目 | みょうがたけ | 茗荷 |
|---|---|---|
| 学名 | Zingiber mioga | Zingiber mioga |
| 利用部位 | 根・葉 | つぼみ(花茎) |
| 味の特徴 | 辛味・香り | 爽やかで独特な香り |
| 料理法 | 炒め物、煮物 | 酢の物、薬味、おひたし |
まとめ
みょうがたけと茗荷は、同じショウガ科の植物ですが、利用できる部位や味わい、料理法などに違いがあります。料理において、その特徴を活かすことで、より美味しく楽しむことができます。ぜひ、みょうがたけと茗荷の違いを知って、次回の食事に取り入れてみてください。
ピックアップ解説
みょうがたけというと、あまりなじみがないかもしれませんが、実は日本の伝統的な食材の一つです
みょうがたけは、その風味が独特で、炒め物や煮物によく使われます
しかし、茗荷はそのつぼみを生で食べることが多く、酢の物や薬味として大活躍します
この二つの違いは、葉や根を食べるのか、つぼみを食べるのか、という点です
どちらも健康にも良い食材なので、積極的に取り入れてみてください!
前の記事: « みょうがとらっきょうの違いを徹底解説!あなたの知らない特徴とは?