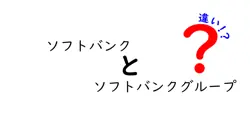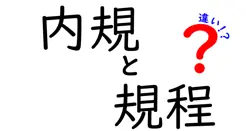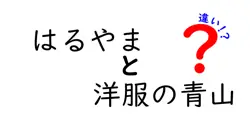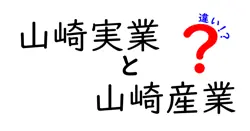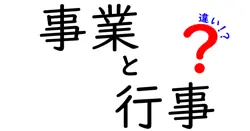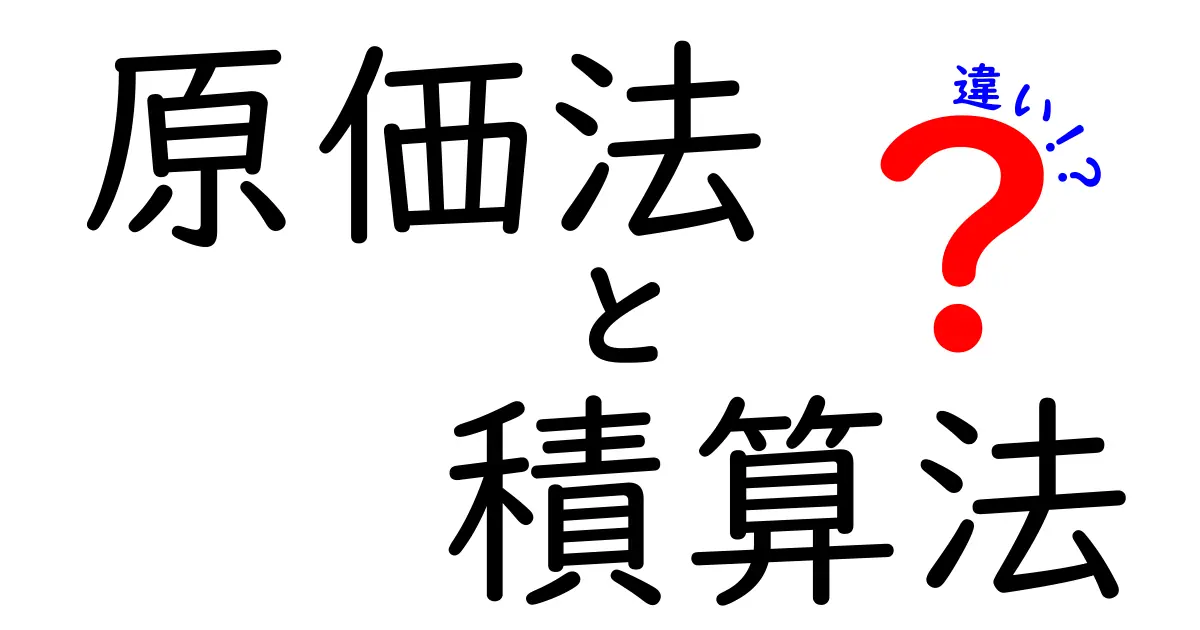
原価法と積算法の違いとは?わかりやすく解説!
ビジネスや経済において、原価法と積算法という言葉を耳にすることがあるでしょう。これらの用語は特に会計や在庫管理の領域で重要です。しかし、これらの違いについてはあまり知られていないかもしれません。ここでは、中学生でも理解できるように原価法と積算法の違いについて解説します。
原価法とは?
原価法というのは、製品を作るためにかかった費用を記録・管理する方法です。具体的には、製品が完成するまでにかかる材料費や人件費、設備費などを「原価」として計上します。たとえば、あるお菓子を作るために必要な砂糖や小麦粉の代金、製造にかかる労力をすべて合計して、そのお菓子の原価を算出します。
積算法とは?
一方で、積算法は原価法と異なり、会計における在庫評価の方法の一つです。特に、販売した商品の価格を計算する際に、どの在庫から売上を算出するかを決めるために使われます。たとえば、Aという商品を100個仕入れ、次にBという異なる仕入れ価格でさらに100個仕入れた場合、販売する際にはどの商品から販売数や売上金を算出するかが重要になります。
原価法と積算法の比較
| 項目 | 原価法 | 積算法 |
|---|---|---|
| 目的 | 製品の原価を把握する | 在庫評価の方法 |
| 利用する場面 | 製品開発、コスト管理 | 会計、売上計算 |
| 記録の方式 | 原材料や人件費を記録 | 個々の在庫単価を記録 |
このように、原価法と積算法はそれぞれ異なる目的と役割を持っています。原価法は製品の製造コストを把握するために用いられ、積算法は売上の計算においてどの在庫を使うかを決定するために使われます。
まとめ
経済やビジネスの分野において、原価法と積算法は非常に重要な手法です。それぞれの特徴を理解することで、ビジネスの運営や経営管理をより効率的に行うことが可能になります。
原価法は製品ができるまでのコストを計算する手法ですが、一方で積算法は在庫の評価と管理に関わる非常に専門的な方法です
在庫を持つ企業にとっては、積算法を知らないと在庫のコストを不正確に計算してしまい、利益にも大きな影響を及ぼすことがあります
実際、どの方法を選ぶかは、その企業の業態や商材によって大きく変わってくるので、非常に頭を使う部分でもありますね
前の記事: « 原価法と時価法の違いを解説!どちらが適切?
次の記事: 取得価額と簿価の違いを簡単に解説!理解しておきたいお金の話 »