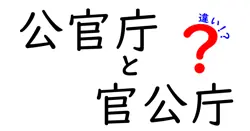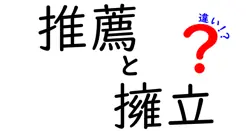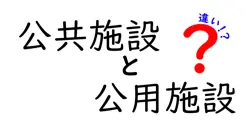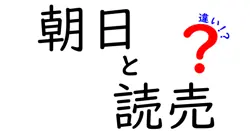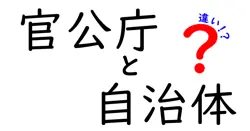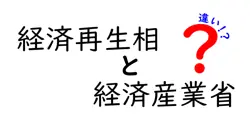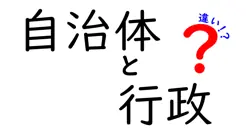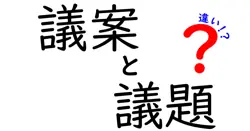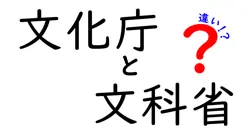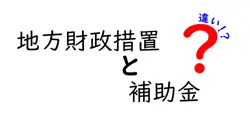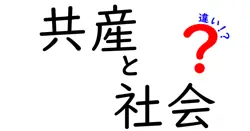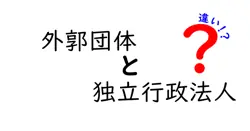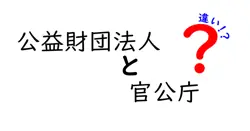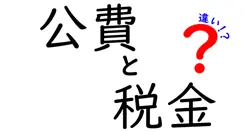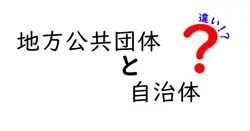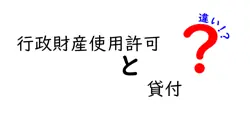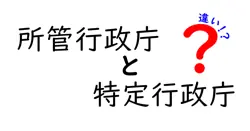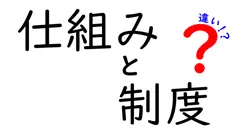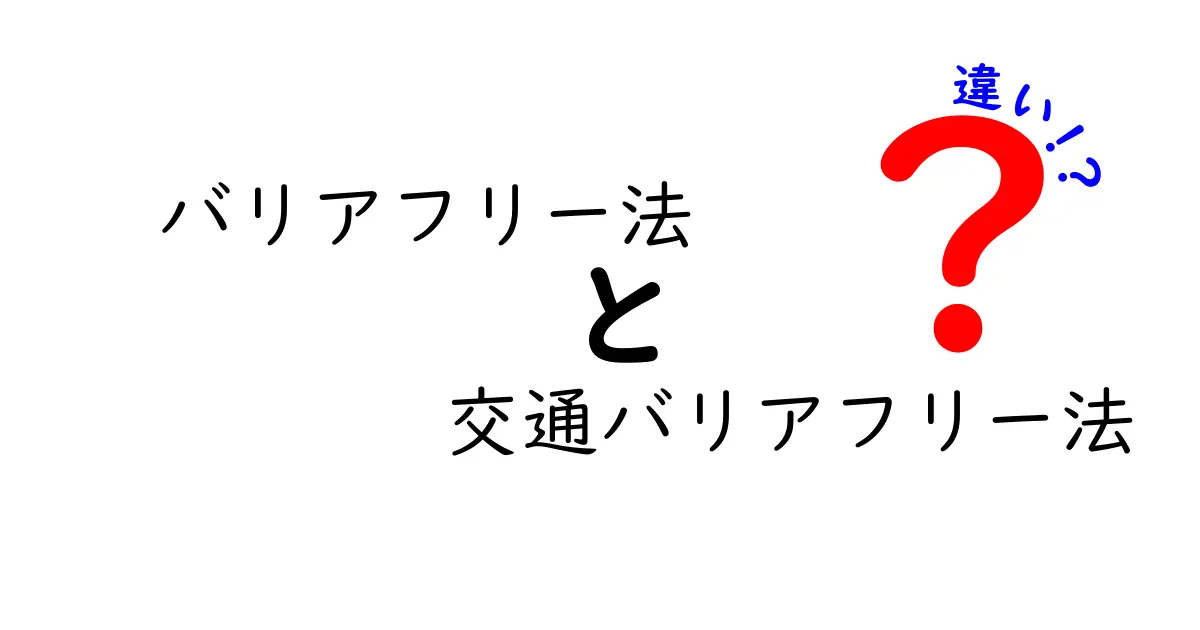
バリアフリー法と交通バリアフリー法の違いをわかりやすく解説!
私たちが生活する中で「バリアフリー」という言葉をよく耳にします。この言葉は、障害のある人や高齢者など、すべての人が快適に過ごせる社会を目指す取り組みを指します。しかし、同じような言葉である「交通バリアフリー法」というものがあり、これら二つの違いについて知っている人は少ないかもしれません。そこで、この記事では、バリアフリー法と交通バリアフリー法の違いを詳しく説明します。
バリアフリー法とは何か?
バリアフリー法は、2000年に施行された法律で、身体障害者や高齢者が生活しやすい環境を整えるための法律です。この法律は、建物や公共の場において、段差をなくしたり、エレベーターやスロープを設置したりすることを含みます。
交通バリアフリー法とは何か?
一方、交通バリアフリー法は、2006年に施行された法律です。この法律は、公共交通機関のアクセシビリティを向上させることを目的としています。具体的には、バスや電車に車椅子でも利用できるようにすることや、駅の構内にエレベーターやエスカレーターを設置することが含まれます。
バリアフリー法と交通バリアフリー法の主な違い
| 項目 | バリアフリー法 | 交通バリアフリー法 |
|---|---|---|
| 目的 | 生活環境の改善 | 公共交通機関の改善 |
| 施行年 | 2000年 | 2006年 |
| 対象 | 建物や公共施設 | バス、電車、駅 |
まとめ
バリアフリー法と交通バリアフリー法は、どちらも障害者や高齢者が快適に過ごせるようにするための法律ですが、その対象や目的は異なります。バリアフリー法は生活環境全般に焦点を当て、交通バリアフリー法は公共交通機関のアクセシビリティに特化しています。これらの法律があることで、より多くの人々が快適に過ごせる社会が実現できることが期待されます。
バリアフリー法について深く掘り下げて考えると、ただ単に障害者や高齢者に優しい環境を作るだけではなく、私たちの生活全般に影響を与えることが分かります
例えば、スロープが整備されることで、ベビーカーを押す親や買い物袋を持った人も移動しやすくなりますね
また、バリアフリー法は最近では「ユニバーサルデザイン」として、障害の有無を問わずすべての人が利用しやすいデザインを推進する考え方も含まれています
このように、バリアフリーは社会全体を便利にしてくれる重要な要素です
前の記事: « バリアフリー条例とバリアフリー法の違いをわかりやすく解説!
次の記事: A型事業所と障害者雇用の違いについてわかりやすく解説します »