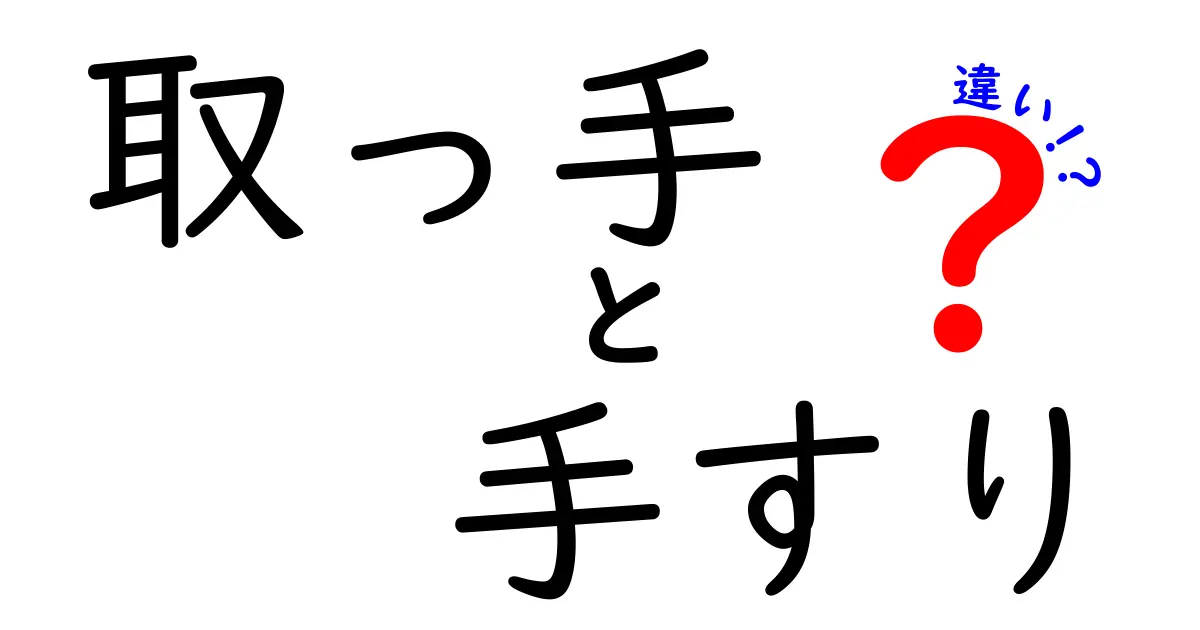
取っ手と手すりの違いは?それぞれの役割と使い方を徹底解説!
生活の中で「取っ手」と「手すり」という言葉をよく聞きますが、実はこの二つは異なるもので、それぞれ異なる役割を持っています。今回は、中学生でもわかりやすく解説していきます!
取っ手とは?
取っ手は、扉や引き出しなどを開けるために取り付けられている部品です。手でつかむ部分があり、物を引いたり押したりするために使います。取っ手の種類には、ドアノブやレバー型のものなどがあり、見た目もさまざまです。
手すりとは?
一方、手すりは、階段やバルコニーなどに取り付けられているもので、主に人が支えられるためのものです。手すりを握ることで、歩く際のバランスを取ることができ、安全性を高める役割があります。手すりは、階段の横に設置されているものが一般的ですが、最近では住宅の廊下やお風呂場にも取り付けられることが増えています。
取っ手と手すりの主な違い
| 特徴 | 取っ手 | 手すり |
|---|---|---|
| 目的 | 物を開けるため | 安全に歩くための支え |
| 設置場所 | 扉や引き出し | 階段やバルコニー |
| 動作 | 引く・押す | 握る・支える |
まとめ
このように、取っ手と手すりは異なる役割を持っています。取っ手は主に物を開けるために使われる一方、手すりは安全を確保するために設けられるものです。何気なく使っているこれらの部品ですが、それぞれの重要な役割を理解することで、より安全で便利な生活を送ることができるでしょう。
ピックアップ解説
取っ手と手すりは一見似ているようですが、実はその目的や使い方が大きく異なります
例えば、取っ手はドアや引き出しを開けるためにあるのに対し、手すりは私たちが歩くときにバランスを取るためのものです
面白いことに、取っ手のデザインは様々ですが、手すりは機能性重視でシンプルなことが多いですね
これが日常の中での『使う場所』による違いなんです
前の記事: « 作業所と障害者雇用の違いを分かりやすく解説!
次の記事: 地域密着型通所介護と通所介護の違いをわかりやすく解説! »





















