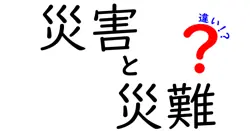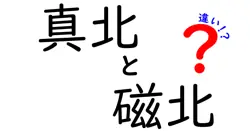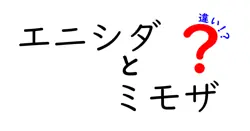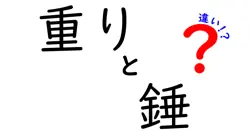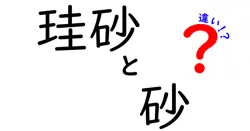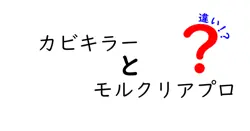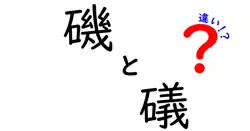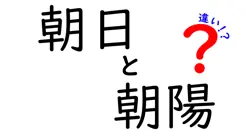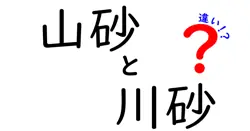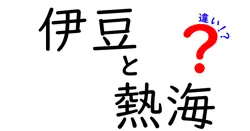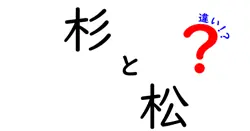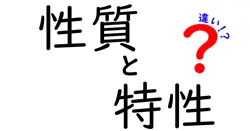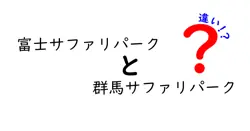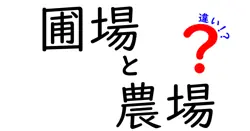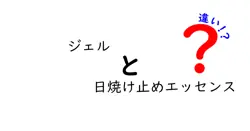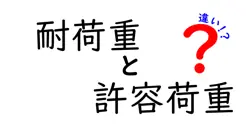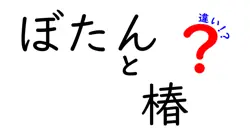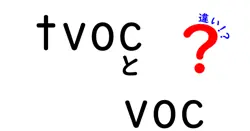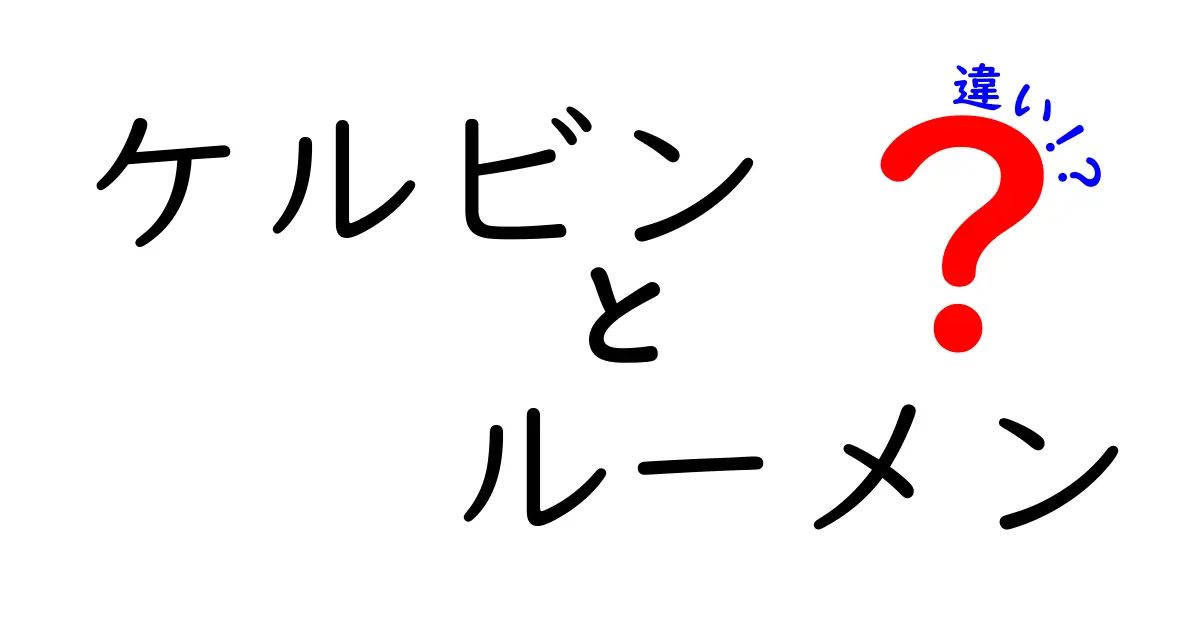
ケルビンとルーメンの違いを徹底解説!光の世界の秘密
私たちの日常生活では、照明やディスプレイの明るさに関する言葉をよく耳にします。その中でも特に重要なのが「ケルビン」と「ルーメン」という2つの単位です。今日は、この2つの違いについてわかりやすく説明していきます。
1. ケルビンとは?
ケルビン(K)は、光の色温度を表す単位で、光の色合いがどのように見えるかを示しています。数値が低いほど、光の色は暖かい(黄っぽい)色合いになり、高いほど寒色系(青っぽい)になります。例えば、キャンドルの光は約1500K、太陽の日中の光は約5500K、青白いLEDは約6500Kという具合です。
2. ルーメンとは?
ルーメン(lm)は、光の明るさを表す単位で、ある光源が放出する光の量を示しています。ルーメンの数値が高いほど、より多くの光を放出することを意味します。例えば、一般的なLED電球は800ルーメンの明るさを持っていますが、これは通常の白熱電球と同等の明るさになります。
3. ケルビンとルーメンの違い
| 要素 | ケルビン (K) | ルーメン (lm) |
|---|---|---|
| 用途 | 光の色温度 | 光の明るさ |
| 数値が高いと | 青白くなる | 明るさが増す |
| 例 | 5500Kは中間の明るさ | 800lmは一般的な電球の明るさ |
4. 具体例で考えてみよう
具体的な例を挙げると、デスクランプを選ぶ時、3000Kの電球(温かい光)もあれば、6000Kの電球(冷たい光)もあります。これに加えて、各電球が持つルーメン数によって、どのくらい明るいのかを数値で判断することができます。
まとめ
今回は、ケルビンとルーメンの違いについて解説しました。ケルビンは光の色を、ルーメンはその明るさを表す単位です。この2つの単位を理解することで、より良い照明選びができるようになるでしょう。
ケルビンについてちょっと面白い話をしますね
実は、ケルビンは温度を示す単位としても使われますが、光の色温度を扱うときには独特な役割を果たします
例えば、ろうそくの光は約1500Kで、暖かく柔らかい雰囲気を持つそうです
一方で、昼間の太陽の光は5500Kから6500Kとされ、こちらは明るくはっきりとした色調を持っています
実際、照明を選ぶ際にこの「ケルビン」の値を知っていると、リラックスしたい雰囲気を作るために適した照明を見つけやすくなりますよ!
前の記事: « 100ルーメンの光量と他のルーメン数の違いとは?
次の記事: メタメリズムと演色性の違いとは?わかりやすく解説! »