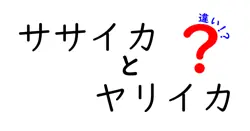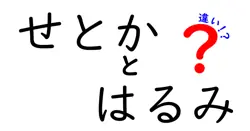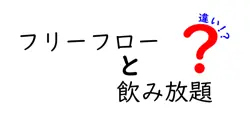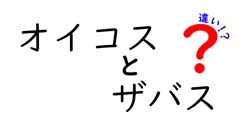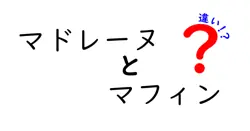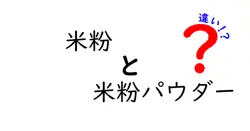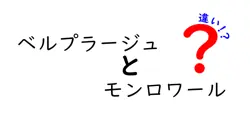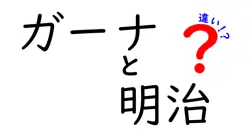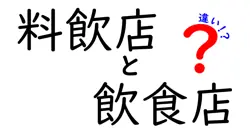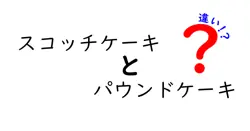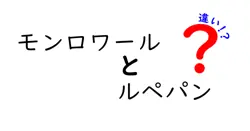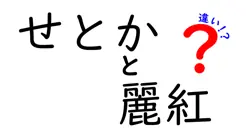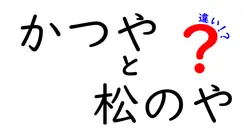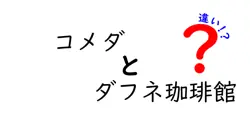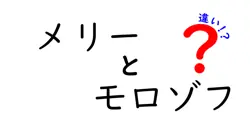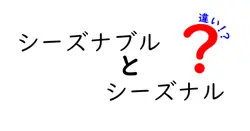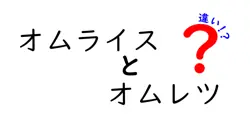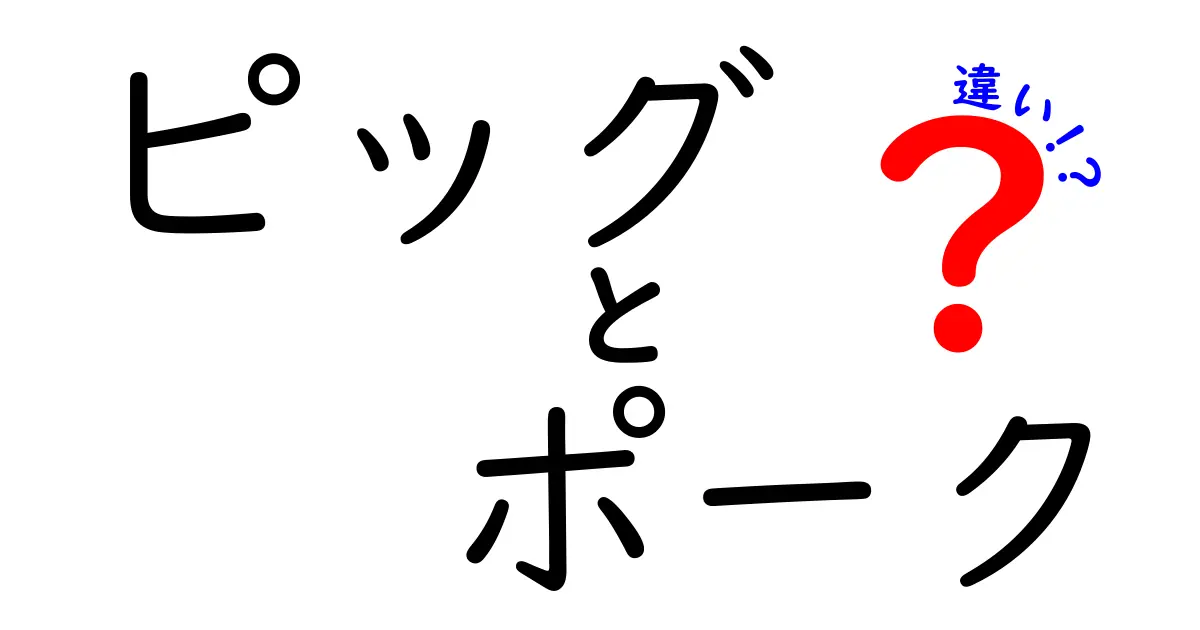
「ピッグ」と「ポーク」の違いを理解しよう!食文化や語源に迫る
私たちの食卓によく登場する「豚肉」。この豚肉には「ピッグ」と「ポーク」という2つの異なる言葉が使われます。今日は、この2つの言葉の違いや、語源、その背景に迫ってみましょう。
ピッグとは?
「ピッグ」とは、英語で「豚」を指す言葉です。一般的には、生きている動物を指します。豚は、家畜として広く飼育されており、その肉や皮は料理に利用されるほか、農業においても重要な役割を果たしています。
ポークとは?
一方、「ポーク」は豚の肉を指す言葉です。料理や食材としての豚肉を示す際に使われ、肉としての側面を強調します。たとえば、「ポークカレー」や「ポークソテー」など、料理名の中でよく見かけます。
ピッグとポークの違い
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ピッグ | 生きている豚を指す |
| ポーク | 豚の肉を指す |
語源の違い
「ピッグ」は古英語の「picg」に由来し、古くから用いられてきましたが、豚の肉を表す「ポーク」は、ラテン語の「porcus」に由来します。このような語源の違いが、使い方にも影響を与えています。
食文化における位置づけ
食文化において、「ポーク」は多くの料理に使われているため、より身近な存在となっています。例えば、バーベキューやお歳暮のギフトなど、ポークは人々に愛され続けています。
まとめ
「ピッグ」と「ポーク」の違いは、単に生きている動物か、肉かということにあります。こうした言葉の使い方を理解することで、食に対する見方が広がります。ぜひ、次に豚肉を食べるときに、これらの用語を思い出してみてください!
ピッグという言葉を聞くと、どうしても動物としての豚をイメージしますよね
しかし、ピッグとポークという言葉の背景には、違った食文化があることをご存じでしたか?実は、世界中で豚肉が好まれる理由は、その味わいだけでなく、豚が非常に多くの部位を持っているため、いろいろな料理に使えるからなんです
日本では、豚カツや餃子、さらにはおでんなど、さまざまな料理で活躍しています
ピッグとポーク、言葉の違いを知ると、もっと食べたくなりませんか?
前の記事: « ハラスとポークの違いを徹底解説!美味しさと特徴を知ろう