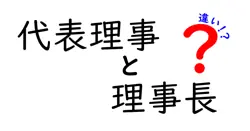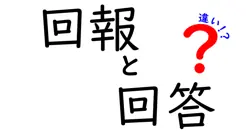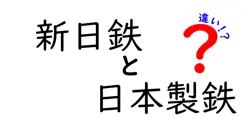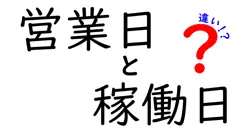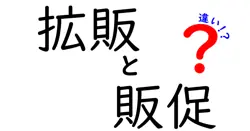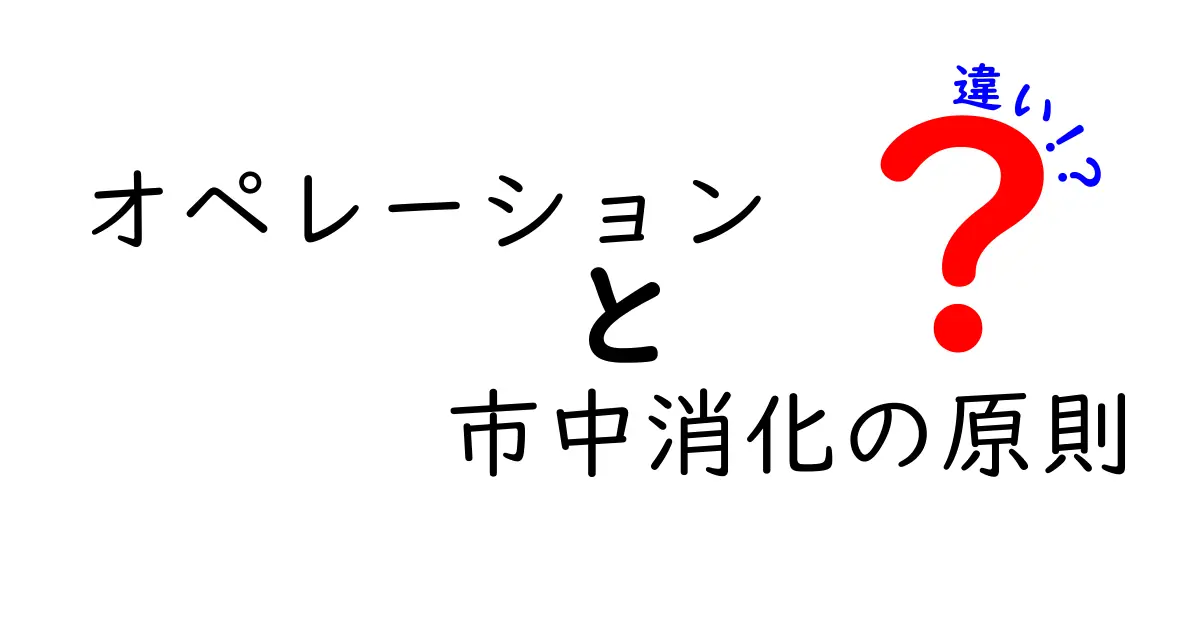
オペレーションと市中消化の原則の違いをわかりやすく解説!
私たちが日常生活で目にする「オペレーション」や「市中消化の原則」。これらの言葉は、特にビジネスや経済の分野でよく使われますが、具体的には何を意味し、どのように異なるのでしょうか?この記事では、その違いについて詳しく見ていきます。
オペレーションとは?
オペレーションは、英語の「operation」からきており、主に「作業」や「運営」を意味します。特にビジネスの文脈では、製品やサービスを効率良く提供するためのプロセスや手続きを指します。例えば、製造業の工場では、製品を生産するための流れや役割分担がオペレーションにあたります。
市中消化の原則とは?
一方で、市中消化の原則は、経済やビジネスの分野において、製品やサービスが市場でどのように受け入れられ、消費されるかという原則です。これは、消費者のニーズや市場のトレンドに基づいています。つまり、市場で販売される商品が消費者にどれだけ受け入れられるかが重要なのです。
オペレーションと市中消化の原則の違い
| 項目 | オペレーション | 市中消化の原則 |
|---|---|---|
| 定義 | 作業や運営のプロセス | 市場での消費の仕組み |
| 主な焦点 | 効率性 | 消費者の受け入れ |
| 適用分野 | 製造業やサービス業 | マーケティングや経済学 |
まとめに代えて
オペレーションと市中消化の原則は、一見するとビジネスに関連する異なる概念ですが、実は密接に関連しています。効率的なオペレーションがあってこそ、製品は市場で受け入れられ、市中消化が進むのです。これらの違いを理解して、ビジネスや経済についての理解を深めていきましょう。
オペレーションというと、なんとなく難しそうに感じるかもしれませんが、実際は私たちの日常生活にも関わっています
たとえば、家庭で晩ご飯を作るときにもオペレーションが関わりますよね
買い物をして、食材を下ごしらえして、調理をする
これらの行動を効率よく行うことで、短時間でおいしい料理が完成します
つまり、オペレーションとは日常生活の中にもたくさん存在しているんですよ!
前の記事: « オペレーションとミッションの違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: オペレーションと運用の違いとは?わかりやすく解説します! »