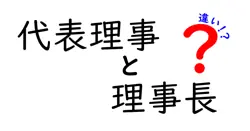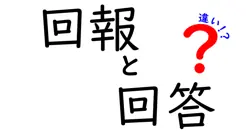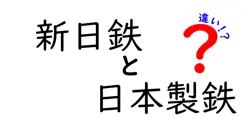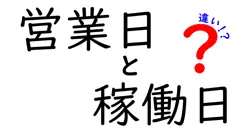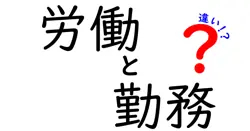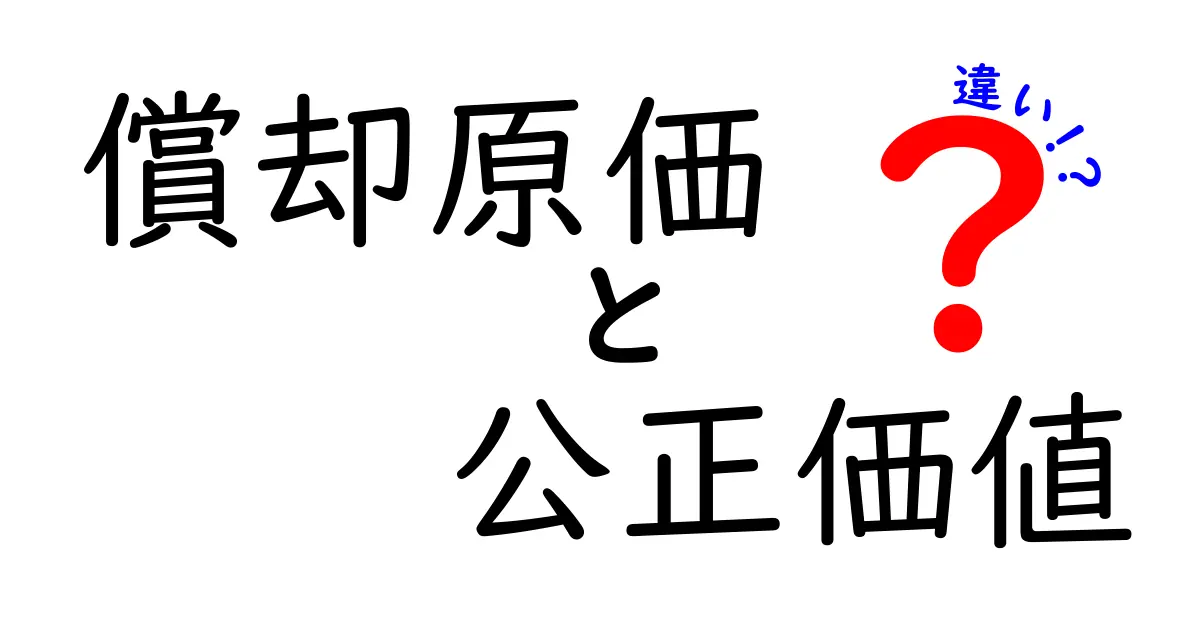
償却原価と公正価値の違いをわかりやすく解説!
私たちは日常生活でさまざまな物を買います。たとえば、スマートフォンやテレビ、家具などです。これらの物はお金を払って手に入りますが、時間が経つにつれてその価値は変化します。そこで重要なのが「償却原価」と「公正価値」です。今回はこの二つの概念について、わかりやすく説明します。
償却原価とは?
まず、償却原価について説明します。償却原価とは、長期間使用される資産の「価値の減少」をお金で表したものです。たとえば、あなたが新しいパソコンを10万円で買ったとします。このパソコンは数年後には古くなり、性能も落ちてしまいます。そのため、毎年少しずつその価値を計算して、例えば3年で完全に使い切るとすると、毎年約3万3333円ずつの価値が減っていくことになります。この減少分が「償却原価」です。
公正価値とは?
次に、公正価値について見てみましょう。公正価値とは、資産が市場で取引されるときの「適正な価格」を指します。これは、その資産が他者に売却される場合に、一般的に受け入れられるであろう価格です。たとえば、市場での取引がある場合、あなたのパソコンは他の人にいくらで売れるかによって公正価値が決まります。市場の状況や需要によって変わるため、常に一定ではありません。
償却原価と公正価値の違い
では、償却原価と公正価値の違いをまとめてみましょう。以下の表をご覧ください。
| 償却原価 | 公正価値 |
|---|---|
| 長期間にわたる資産の価値の減少を計算したもの | 市場での取引が行われる際の適正価格 |
| 通常、会計処理で用いられる概念 | 市場の需給によって変動する |
| 定期的に計算される | 取引のタイミングによって変わる |
このように、償却原価は資産の使用に伴う価値の減少を意味し、公正価値は市場での取引における価格を指します。一見似ているようで、実はまったく異なる概念です。他人に物を売ったり買ったりする際には、公正価値が重要ですが、会計処理を行う際には償却原価が必要になります。
まとめ
償却原価と公正価値の違いを理解することは、資産管理や投資をする上で非常に重要です。それぞれの特徴を知り、適切に使用することで、より良い意思決定ができるようになります。
償却原価について考えると、実は学校の教科書やノートにもこの考え方が使われているんです
例えば、学生が購入した教科書は3年使った後にはもう古くなって価値が半分以下になっていたりしますよね
これが償却原価です
教育機関でも、この考え方を用いて教材のコストを計算しています
つまり、私たちが学ぶために使う教材でも、償却原価が影響を及ぼしているというわけです
前の記事: « 使用価値と公正価値の違いをわかりやすく解説!