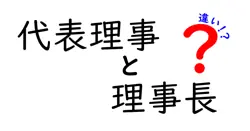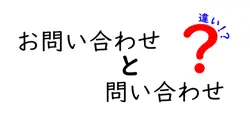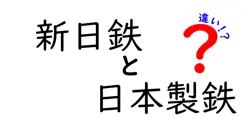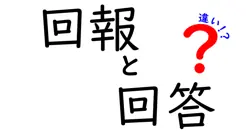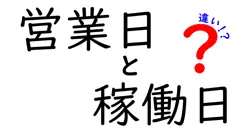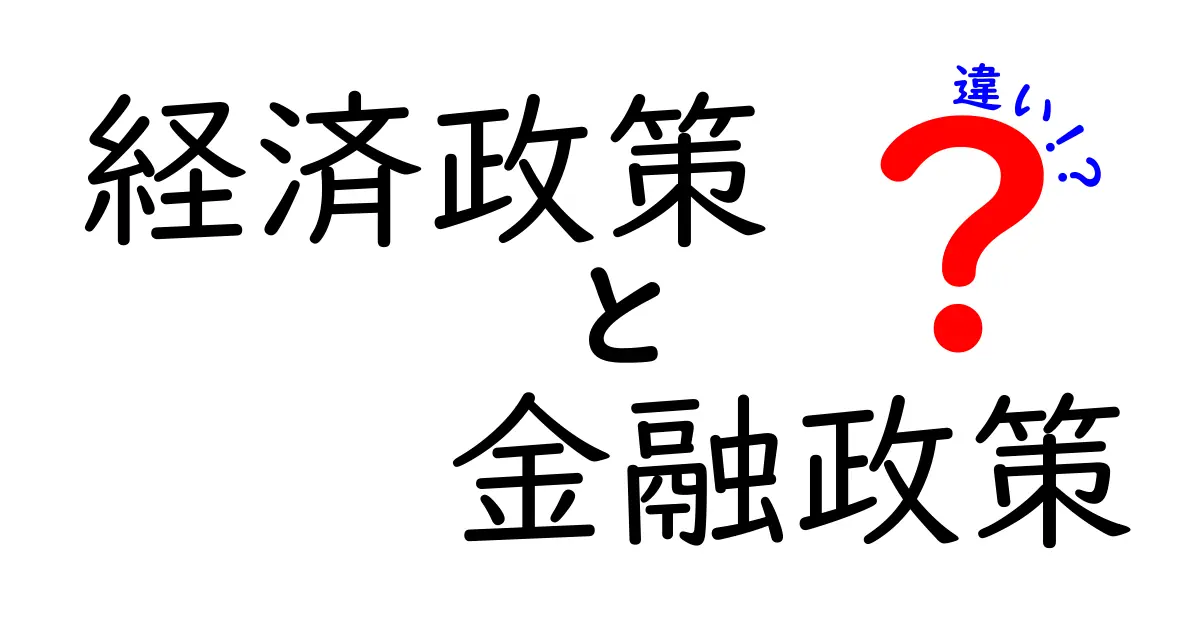
経済政策と金融政策の違いとは?簡単に解説します!
経済政策と金融政策は、国の経済をコントロールするために非常に重要な手段ですが、同じものではありません。この2つの政策の違いを理解することで、経済がどのように動いているのかが見えてきます。ここでは、経済政策と金融政策の概念や役割を詳しく解説していきます。
経済政策とは
経済政策とは、政府が経済の成長を促進したり、景気の安定を図ったりするためのさまざまな施策を指します。これには、税制、公共投資、規制緩和などが含まれます。具体的には、税金を減らして消費を活発にしたり、公共事業を拡大して雇用を生み出したりすることが経済政策の一例です。
金融政策とは
一方、金融政策は中央銀行(例えば日本では日本銀行)が行う政策で、主に金利の調整や貨幣供給量のコントロールを通じて経済に影響を与えます。例えば、金利を下げることで借入がしやすくなり、企業や個人が資金を使いやすくなります。これによって消費や投資が促進され、経済の成長が期待されます。
両者の違いをまとめると
| 項目 | 経済政策 | 金融政策 |
|---|---|---|
| 目的 | 経済成長、雇用創出 | 物価安定、経済安定 |
| 実施機関 | 政府 | 中央銀行 |
| 手段 | 税制改善、公共事業 | 金利操作、貨幣供給量調整 |
このように、経済政策と金融政策には明確な違いがありますが、どちらも経済を安定させ、成長を促進するためになくてはならないものです。経済政策が社会全体の環境を整え、金融政策がその環境の中で資金の流れを操る役割を担っています。
経済政策という言葉には、政府が経済を整えるために行うさまざまな施策が含まれています
しかし、経済政策の効果はすぐに表れないことが多いです
たとえば、公共事業を始めても、実際に効果が出るのは数年後だったりします
だから、実際には長期的な視点が求められるんです
それに対して金融政策は、中央銀行が金利を変えることで、比較的短期間で影響が出やすいのが特徴です
こうした金融政策の一手が、例えばお金を借りやすくすることができ、企業の活動にすぐに良い影響を与えることもあります
だから、経済政策と金融政策は連携して動くことが大切なんですね!
前の記事: « 短期借入と長期借入の違いとは?初心者にもわかりやすく解説!