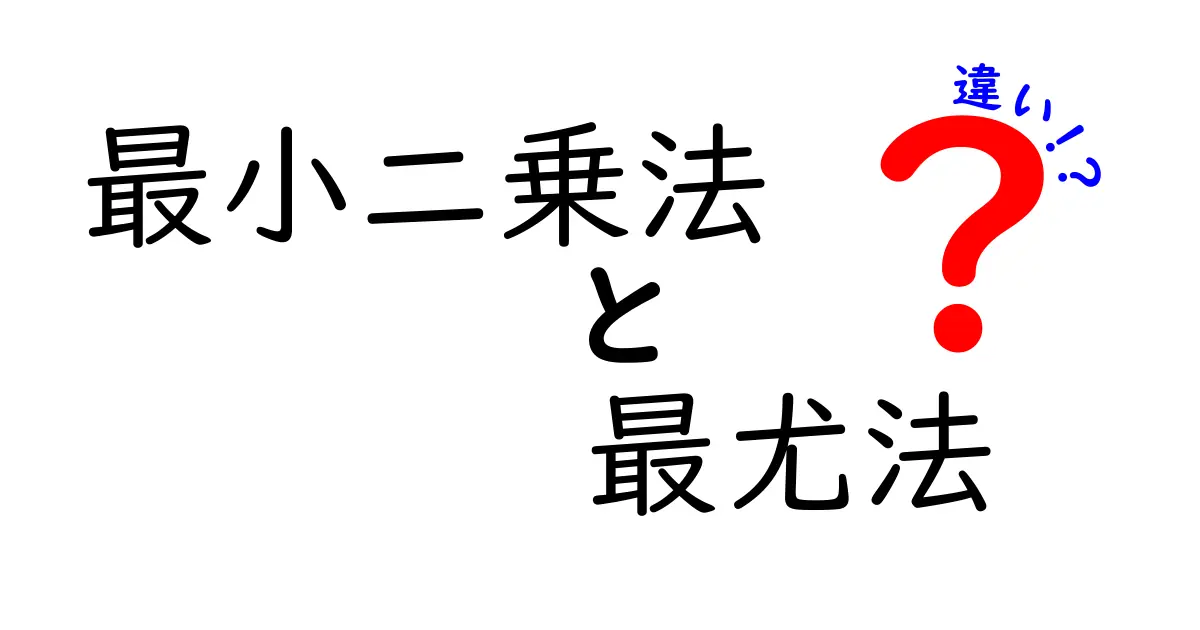
最小二乗法と最尤法の違いをわかりやすく解説!
数学や統計学を学ぶ中で、データ分析やモデルの推定に使われる手法として「最小二乗法」と「最尤法」という二つがあります。この二つの手法は似ているようで、実は異なる特性を持っています。今回は、この二つの違いを中学生にもわかるように解説していきます。
最小二乗法とは?
最小二乗法は、与えられたデータに対して最も適切な直線や曲線を見つけるための方法です。例えば、テストの点数と勉強時間の関係を調べるとき、データを使って「y = ax + b」の形の直線を描くことができます。最小二乗法では、実際のデータポイントとその直線との「距離」を計算し、その距離の二乗の合計が最も小さくなるように直線を調整します。
最尤法とは?
一方、最尤法はデータから確率モデルを推定するための手法です。例えば、あるコインを投げたときに出る表と裏の確率を知りたいとします。ここで、最尤法では、実際のデータ(コインの結果)をもとに、そのデータが最も起こりやすい(最尤)モデルを選びます。つまり、与えられたデータが得られる確率が最大になるようなパラメータを見つけます。
最小二乗法と最尤法の比較
二つの手法の違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 最小二乗法 | 最尤法 |
|---|---|---|
| 目的 | データに対して近似モデルを見つける | データからモデルのパラメータを推定する |
| 計算方法 | 距離の二乗和を最小化 | 確率を最大化 |
| 使用するデータの性質 | 連続データ、線形関係 | 確率分布、離散データ |
まとめ
最小二乗法は主にデータの近似や回帰分析に用いられ、最尤法は確率的なモデルを使ったデータ分析に用いられます。どちらの手法もデータ分析の世界では非常に重要なもので、それぞれの特性を理解することで、より深くデータを解析できるようになります。今後の学びに活かしていきましょう!
最小二乗法は、実は単純な回帰分析だけでなく、データのフィッティングなんかにも広く使われています
例えば、映画の興行成績や商品の売上予測においても、その関係性をモデル化するために使われているんですよ
また、最小二乗法はパターン認識や機械学習の基礎にも活かされています
どういうことかというと、AIがデータを学ぶ際、最小二乗法に基づいて予測モデルを作ることがあるんです
身近なところでも使われているので、ぜひ注目してみてください!
前の記事: « 最小二乗法と最小領域法の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 最小二乗法と相関係数の違いを簡単に解説!データ分析の基礎を知ろう »





















