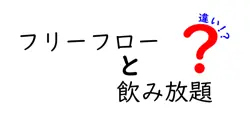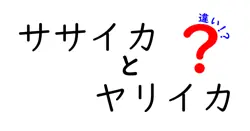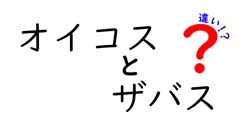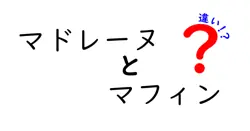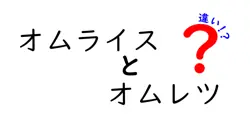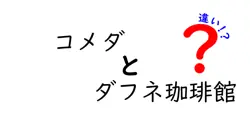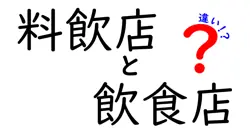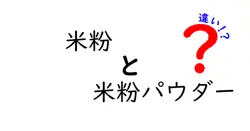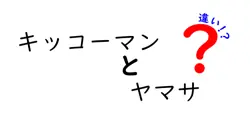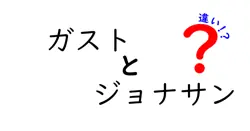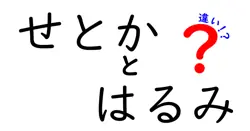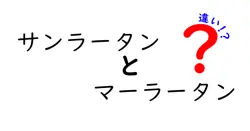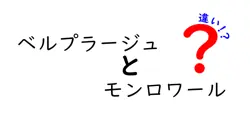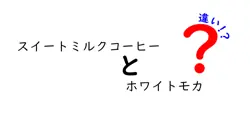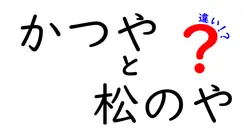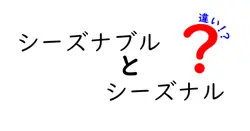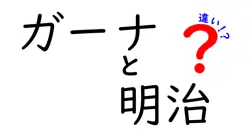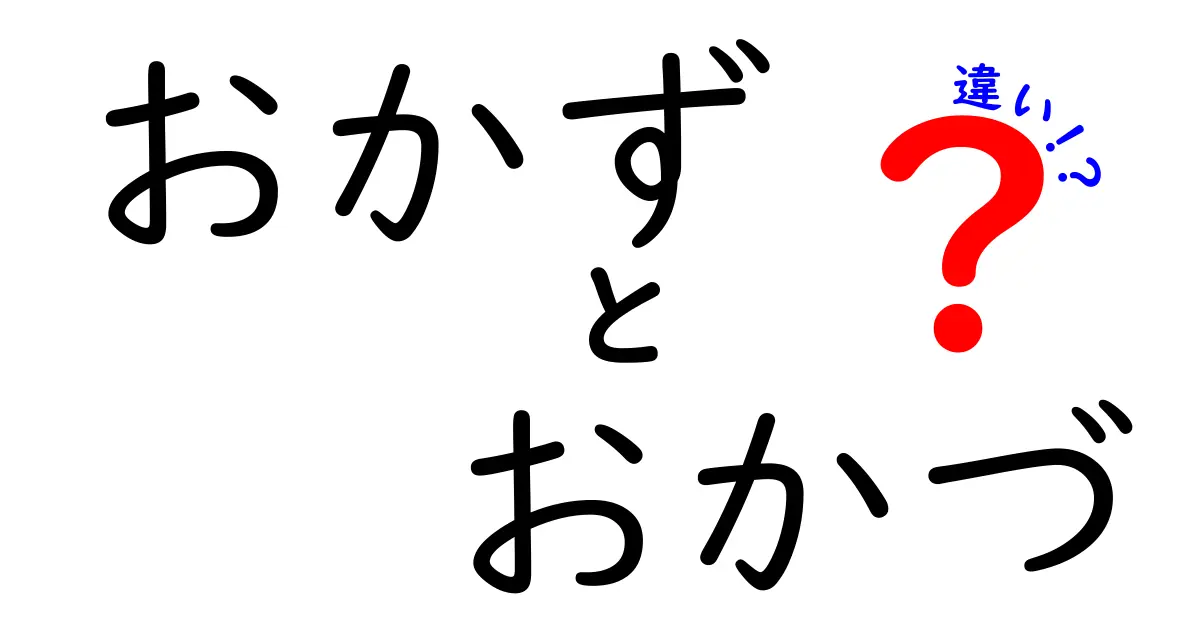
「おかず」と「おかづ」の違いは?意味や使い方を徹底解説!
みなさんは「おかず」と「おかづ」という言葉を聞いたことがありますか?実は、これらの言葉は日本の食文化においてとても重要です。しかし、見た目は似ていても意味が異なるのです。今日はこの二つの言葉について詳しく見ていきましょう。
「おかず」の意味
まず「おかず」ですが、これは主に食事の際にご飯と一緒に食べる料理や食材を指します。例えば、焼き魚や卵焼き、煮物などが「おかず」として一般的です。ここでポイントなのは、「おかず」は料理そのものを指すだけでなく、その種類やスタイルも意味しています。
「おかづ」の意味
次に「おかづ」ですが、実は「おかず」とは違い、一般的には使われていない言葉です。しかし、地域や特定のコミュニティでは「おかづ」という言い方が使われることもあります。具体的には、土佐地方など一部の地域で見られる表現で、その地方では「おかず」と同じ意味合いを持つことが多いです。
「おかず」と「おかづ」の使い方
| 言葉 | 説明 |
|---|---|
| おかず | 主にご飯に合わせて食べる料理や食材 |
| おかづ | 地域的な表現で「おかず」を指す場合がある |
まとめ
いかがでしたでしょうか?「おかず」と「おかづ」は言葉として耳にすることはあっても、その使われ方は少し異なります。日常生活の中で意識してみると、言葉の面白さが感じられるかもしれません。これから、あなたの食事にも「おかず」を意識して取り入れてみてください。そして、地域の文化も大切にしていきたいですね。
「おかず」と「おかづ」の違いについて考えていると、食文化の豊かさを感じさせられますよね
例えば、同じおかずでも地域によっては、全く違う料理が出てくることもあります
おばあちゃんの家での手作り料理は、家庭の味として特別ですよね
そんな背景の中で「おかづ」という言葉が使われる地域があるというのは、文化の多様性を感じさせてくれます
食べ物の言葉の違いから、地域の歴史や人々の生活が見え隠れするのが面白いところです
前の記事: « 「st」と「時短」の違いを徹底解説!あなたの生活が変わるかも?
次の記事: おかずと料理の違いを徹底解説!知って得する食の知識 »