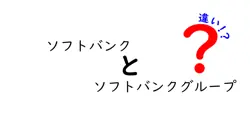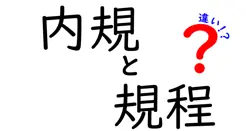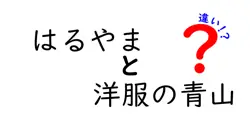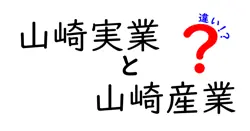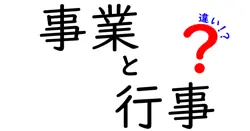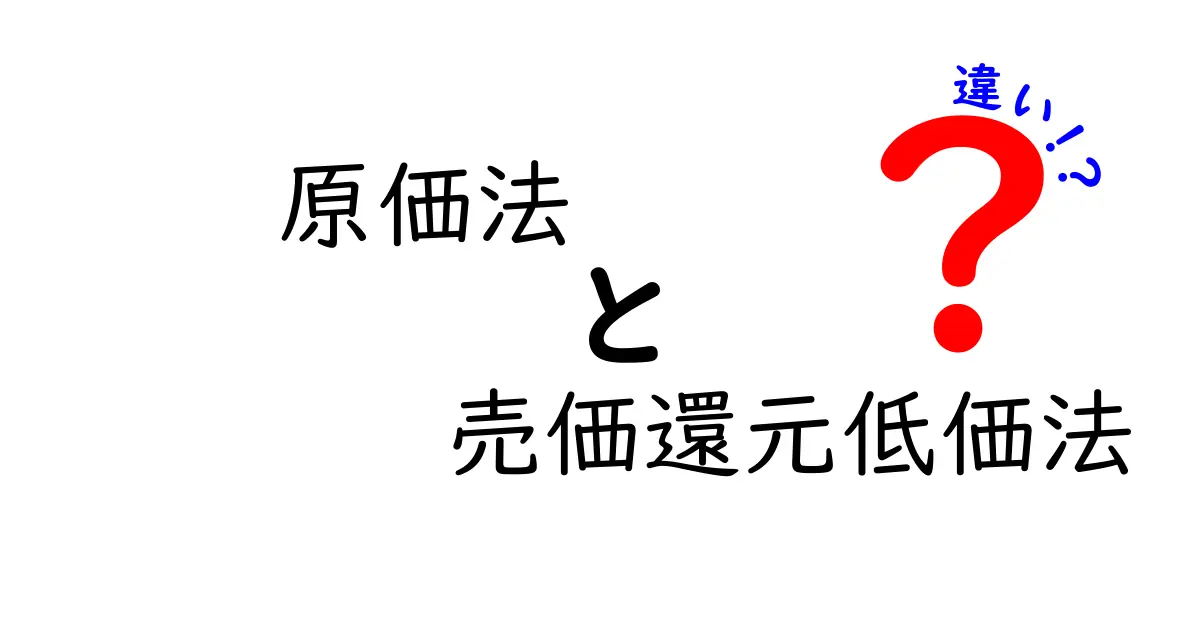
原価法と売価還元低価法の違いを徹底解説!
皆さん、ビジネスをする上で、商品の価格設定ってとても大事ですよね。今日は、「原価法」と「売価還元低価法」という二つの価格算出の方法について、お話ししたいと思います。中学生でもわかりやすく説明しますので、一緒に学びましょう!
原価法とは?
まずは「原価法」からです。原価法とは、商品を販売する際に、その商品の製造や仕入れにかかったコストを基に価格を設定する方法です。つまり、原材料費や労働費用、その他の運営費用をしっかり考慮して、その合計に利益を乗せて価格を決めます。
売価還元低価法とは?
次に「売価還元低価法」を見てみましょう。この方法は、最初に設定した売価から必要な利益や経費を引いて、商品の価格を算出する方法です。販売価格が先に決まっている場合、この方法を使うことで、どれくらいのコストで商品を作れるかを逆算することになります。
原価法と売価還元低価法の違い
| 特徴 | 原価法 | 売価還元低価法 |
|---|---|---|
| 価格設定基準 | コストを基に価格決定 | 売価を基にコスト算出 |
| 利点 | コスト管理が明確 | 販売価格に対応しやすい |
| 欠点 | 市場価格に影響される | コスト管理が難しい場合も |
どちらを使うべきか?
ビジネスを行う上で、どちらの方法を選ぶべきかは、それぞれの状況に依存します。たとえば、コストをしっかり把握したい場合は原価法が効果的です。一方、売上を重視するビジネスモデルでは売価還元低価法が適しているかもしれません。それぞれの特色をうまく活かして、あなたのビジネスに最適な方法を見つけてみましょう!
まとめると、原価法はコストに基づいた価格設定、売価還元低価法は販売価格からコストを逆算する方法です。どちらも一長一短がありますが、しっかりと理解して利用することが成功への第一歩です。
「原価法」という言葉を聞くと、いかにも企業の管理を気にした方法のように思えますよね
でも、原価法が重要なのは、業界によっては原材料の価格が大きく変動するからです
たとえば、農業の分野では、物の価格は季節によって大きく変わることがあります
そういう時、原価法を使うことで、無駄なコストを抑え、効率的な運営ができるようになりますね
だから、原価法はただの計算方法以上のものなんです!