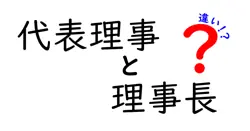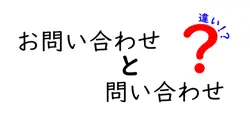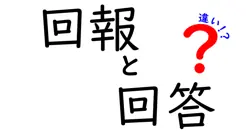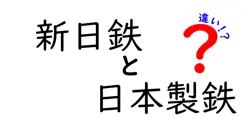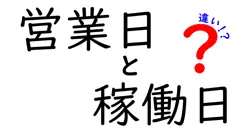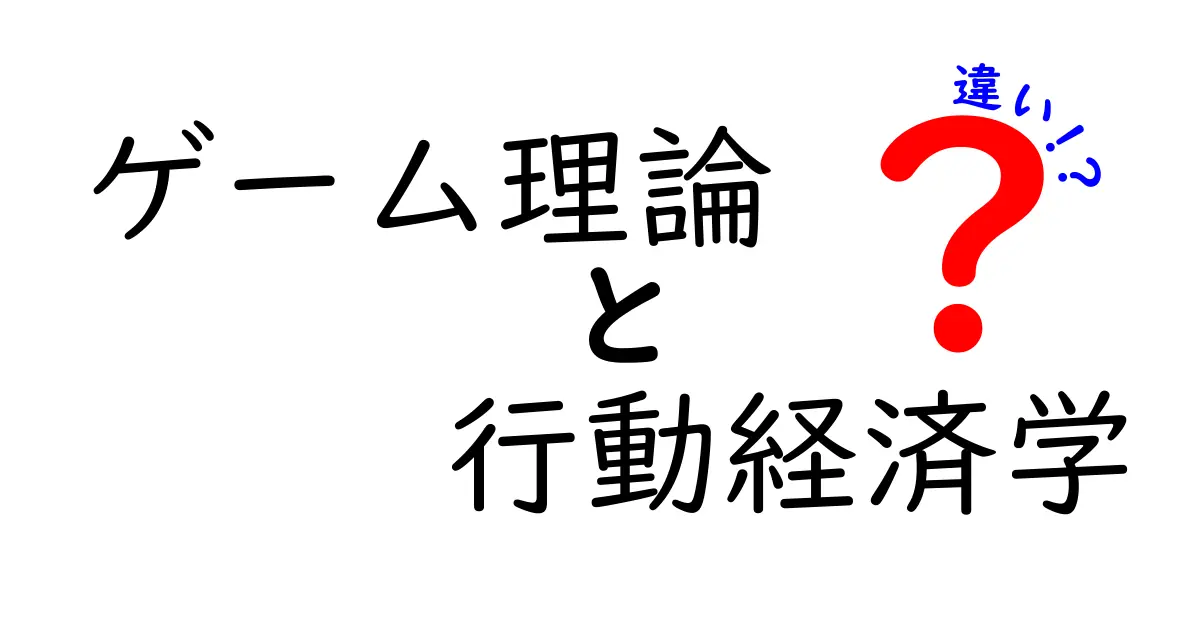
ゲーム理論と行動経済学の違いをわかりやすく解説!
皆さんは「ゲーム理論」と「行動経済学」という言葉を聞いたことがありますか?この二つは経済学や社会科学の中でもとても重要な分野ですが、ややこしいことが多いです。そこで、今日はこの二つの違いについて、簡単に説明していきます。
ゲーム理論とは
ゲーム理論は、プレイヤー(人や団体)が選択をする場面を分析するための理論です。この理論は、数学や論理を使って、各プレイヤーが最適な戦略をどう選ぶかを考えます。例えば、サッカーの試合やビジネスの競争など、様々な「ゲーム」の中での戦略を示します。
行動経済学とは
一方、行動経済学は、人間が経済的な意思決定をする時にどんな心理が働くのかを研究する分野です。人間は必ずしも合理的な選択をするわけではなく、感情やバイアスが影響を与えることが多いです。例えば、買い物する時に「割引セール」という言葉に思わず惹かれてしまうのも、その一例です。
大きな違いは何か?
ゲーム理論は「戦略」を重視し、行動経済学は「心理」を重視します。ここで、表を使って分かりやすくまとめてみましょう。
| 特徴 | ゲーム理論 | 行動経済学 |
|---|---|---|
| 主なテーマ | 戦略 | 心理 |
| 対象 | プレイヤー間の相互作用 | 個人の意思決定 |
| 手法 | 数学的モデル | 実験心理学 |
このように、ゲーム理論と行動経済学はそれぞれの視点から、経済や社会を理解しようとしています。実際のビジネスシーンでも、この二つの理論はとても有用です。例えば、新しい商品を開発する場合、競争相手の戦略を見越すゲーム理論と、消費者の心理を分析する行動経済学の両方を使うことで、より成功しやすくなります。
今回は、ゲーム理論と行動経済学の違いについてお話ししました。これらの知識を使って、日常の選択や戦略を考えると、新しい発見があるかもしれませんね!
ゲーム理論は、古典的には「囚人のジレンマ」という課題が有名です
二人が捕まった囚人が、相手を裏切るか協力するかを選ぶ場面を描いています
この状況で、合理的に考えると互いに裏切る方が安全と思うのですが、実は協力することが最も良い結果をもたらすんですよ
つまり、人は必ずしも合理的な選択をしないということ
これが、ゲーム理論が示す面白いところなんです!
前の記事: « ゲーム理論とミクロ経済学の違いを徹底解説!分かりやすく理解しよう