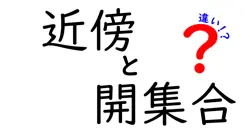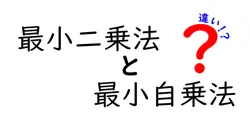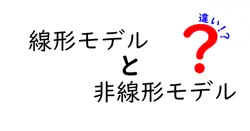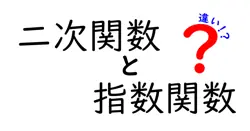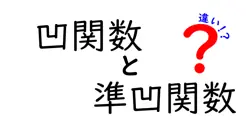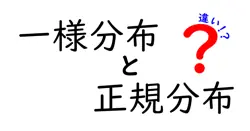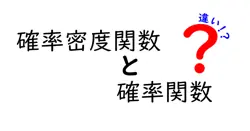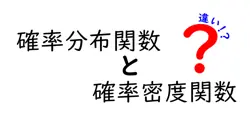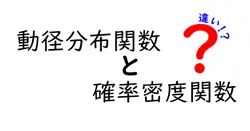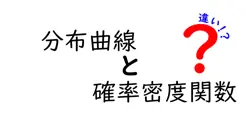両者は数学の基本概念であり、違いを理解することでさらなる数学の学びにつなげられます
自然関連の○○と○○の違い!
両者は数学の基本概念であり、違いを理解することでさらなる数学の学びにつなげられます
主に回帰分析で使われており、データ分析に役立ちます
最小自乗法は日本語の別名に過ぎません
両者の違いを理解することで、データ分析や予測の精度を向上させることができる
二次関数は放物線、指数関数は急激な増加を示します
それぞれの特性を理解して、実際のグラフを描くことが理解を深めるポイントです
凹関数は2点を結ぶ直線が関数の下にあり、最適化に重要です
一方、準凹関数は2点間の中間点がその直線上にあるか、それ以上の値を持ちます
それぞれの性質を理解することで、数学や経済学の問題を解く助けになります
どちらもデータの性質を理解するために重要な概念です
それぞれの使用例や出力方法が異なるため、理解を深めることで確率の考え方が広がります
離散変数には前者、連続変数には後者が使われ、グラフの形も異なる
理解することで確率の考え方が深まる
この2つの概念は異なる用途を持ちながらも、データ分析や物理学において重要です
理解することで、現象の解析が深まります
この二つの概念は異なる目的を持っており、統計の理解に役立ちます