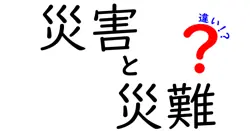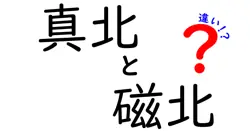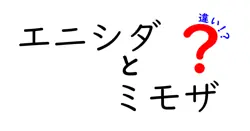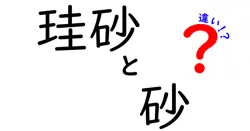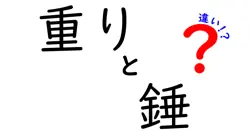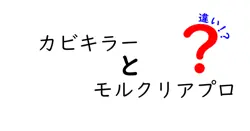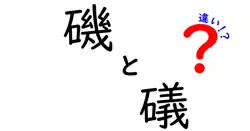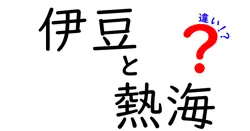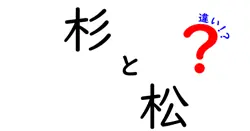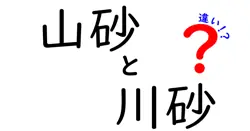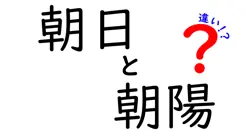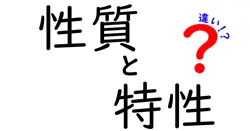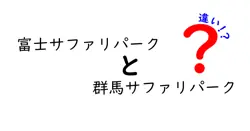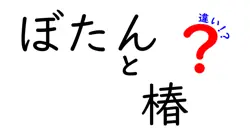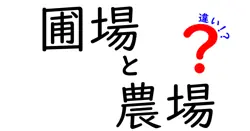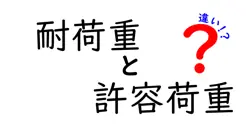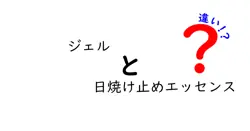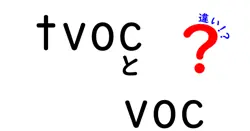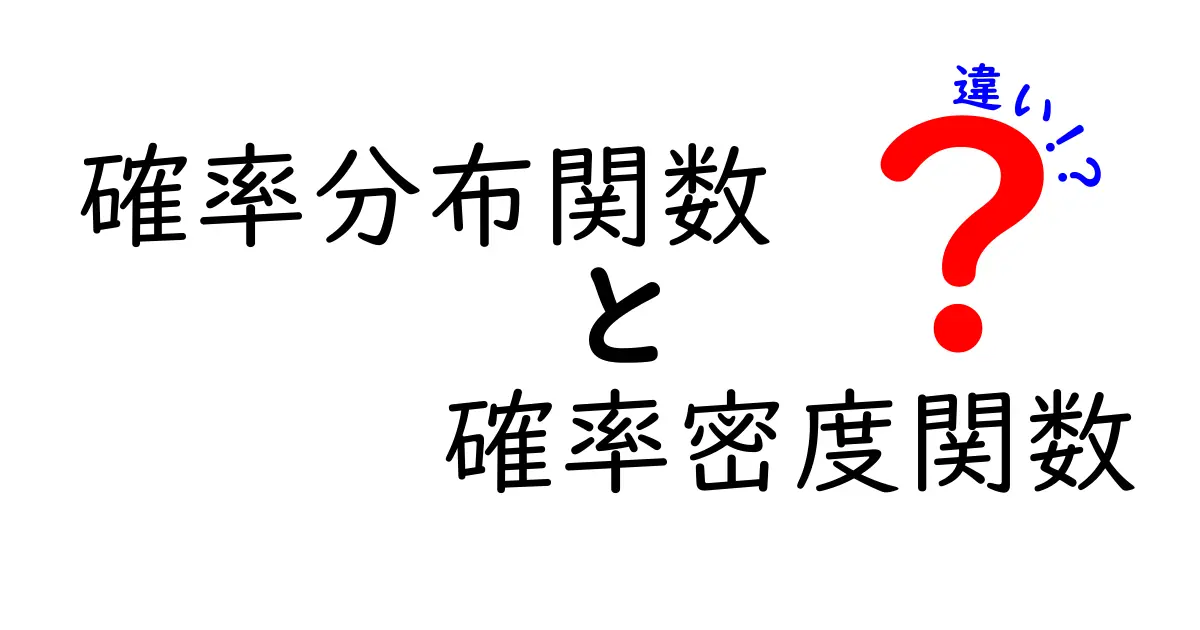
確率分布関数と確率密度関数の違いをわかりやすく解説!
みなさんは、確率分布関数と確率密度関数という言葉を聞いたことがありますか?これらは、確率論という数学の一部分で使われる重要な概念です。今日は、中学生でもわかるように、これらの違いを解説していきます。
確率分布関数とは?
まず、確率分布関数(かくりつぶんぷかんすう)について説明します。確率分布関数は、ある確率変数が特定の値以下になる確率を示す関数のことです。例えば、サイコロを振ったときに出る目の確率分布を考えると、確率分布関数を使うと、2以下の目が出る確率はどれくらいかを数字で示すことができます。
確率密度関数とは?
次に、確率密度関数(かくりつみつどかんすう)について説明します。これは、連続的な確率変数が特定の範囲にある確率を示すための関数です。例えば、身長や体重といった連続的なデータに対して、ある範囲の値がどれくらいの確率で存在するかを知りたい場合に使います。確率密度関数は、面積を使って確率を表します。
確率分布関数と確率密度関数の違い
| 項目 | 確率分布関数 | 確率密度関数 |
|---|---|---|
| 定義 | 特定の値以下の確率を示す | 特定の範囲に存在する確率を示す |
| 対象 | 離散変数 | 連続変数 |
| 表現 | グラフは階段状 | グラフは滑らか |
このように、確率分布関数と確率密度関数は、確率を表現するために使われるものですが、それぞれの特性や用途が異なります。
まとめ
確率分布関数は、離散的な値に対して確率を表示するのに対し、確率密度関数は、連続的な範囲に対する確率を考えるのに使います。これらを理解することで、確率の概念がより深く理解できるようになります。ぜひ、日常生活にもこの考え方を取り入れてみてください!
確率密度関数について少し雑談しましょう
確率密度関数は、身長や体重のデータを考えるときによく使われます
例えば、クラスのみんなの身長のデータを集めると、多くの人が165cm前後に集まっているかもしれません
ここで、確率密度関数を使うと、「165cmから170cmの範囲にいる確率はどれくらいか?」ということが明らかになります
面白いことに、この確率密度のグラフは山の形になり、最も高くなる部分では多くの人が存在することを示します
これを使うことで、人々の特性を可視化できるのが楽しいところです!
前の記事: « 確率分布と確率密度関数の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 確率密度関数と確率質量関数の違いをわかりやすく解説 »