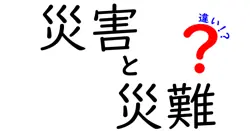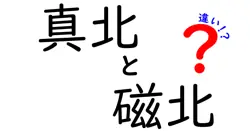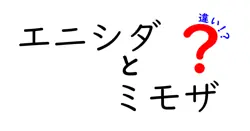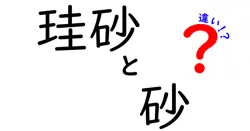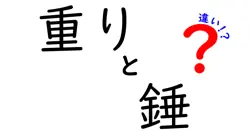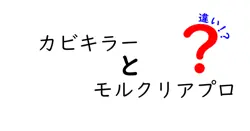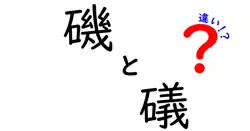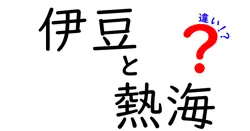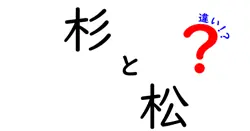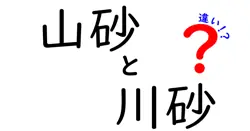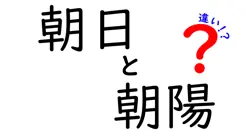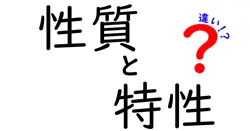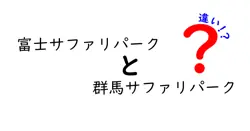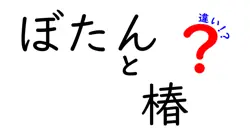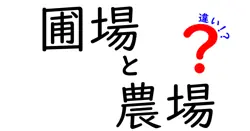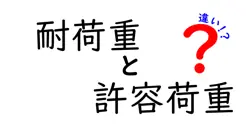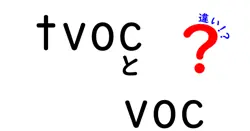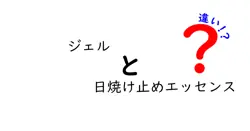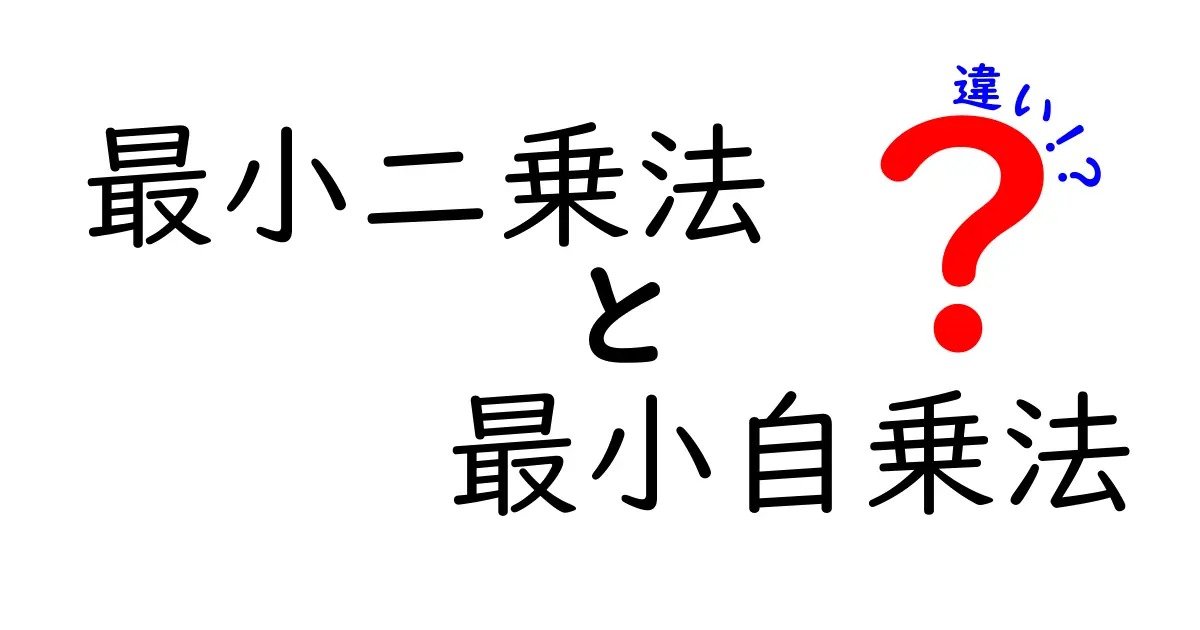
最小二乗法と最小自乗法の違いを徹底解説!どちらを使うべき?
最小二乗法(さいしょうにじょうほう)と最小自乗法(さいしょうじじょうほう)。これらは数学や統計学で使われる手法ですが、一体何が違うのでしょうか?中学生でもわかるように解説します。
最小二乗法とは?
最小二乗法は、与えられたデータ点から最も近い直線(回帰直線)を求める方法です。この方法は、誤差を最小限に抑えるために使われています。具体的には、データ点と直線の距離(誤差)の二乗和を最小化します。この「二乗」を使うことで、誤差が大きい場合の影響を強く受けることになります。
最小自乗法とは?
最小自乗法という言葉は、実は最小二乗法の日本語の異なる言い方に過ぎません。そのため、最小自乗法と最小二乗法は実質的に同じものを指します。どちらも回帰分析に使われ、同様の計算を行います。
最小二乗法と最小自乗法の違い
| 項目 | 最小二乗法 | 最小自乗法 |
|---|---|---|
| 定義 | 誤差の二乗和を最小にする手法 | 最小二乗法と同義 |
| 使用場面 | 回帰分析 | 回帰分析 |
まとめ
最小二乗法と最小自乗法は、実際には同じ意味の言葉です。よく使われる場面は回帰分析で、どちらを使っても同じ結果が得られます。もしデータを分析したい時は、この手法を使ってみると良いでしょう!
最小二乗法を理解するために、少し面白い話をしましょう
想像してみてください
あなたは、友達とバスケットボールをしているとき、シュートの練習をしています
でも、毎回バスケットを外してしまう
どうにかして、シュートをうまく決めたいと思ったとき、あなたはどうするでしょう?そう、練習を重ね、どの位置から投げたときに上手く入るのかをデータとして集める
ここで最小二乗法が役立ちます!それぞれのシュートの誤差を計算し、最も近い『理想的なシュートライン』を見つけるのです
これにより、次回から正確にシュートを決められるようになるかもしれません
まさに、数学は実生活にも活かせるのです!
前の記事: « 最小二乗法と最小絶対値法の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 最小二乗法と最小領域法の違いをわかりやすく解説! »