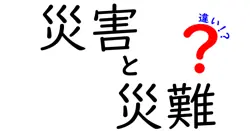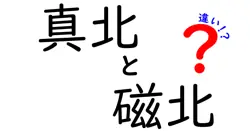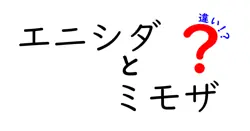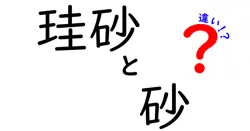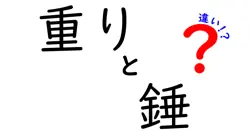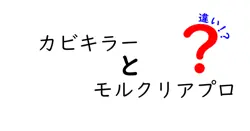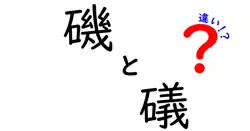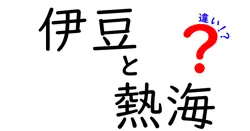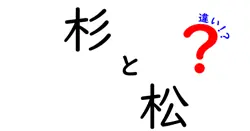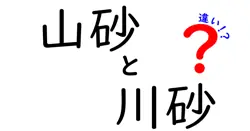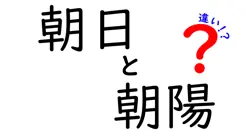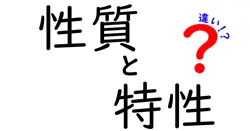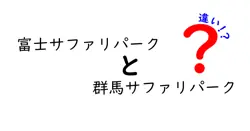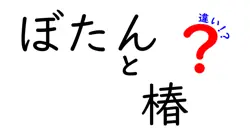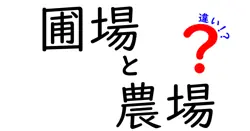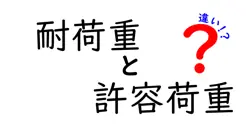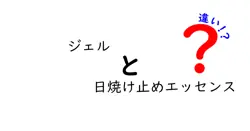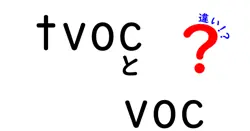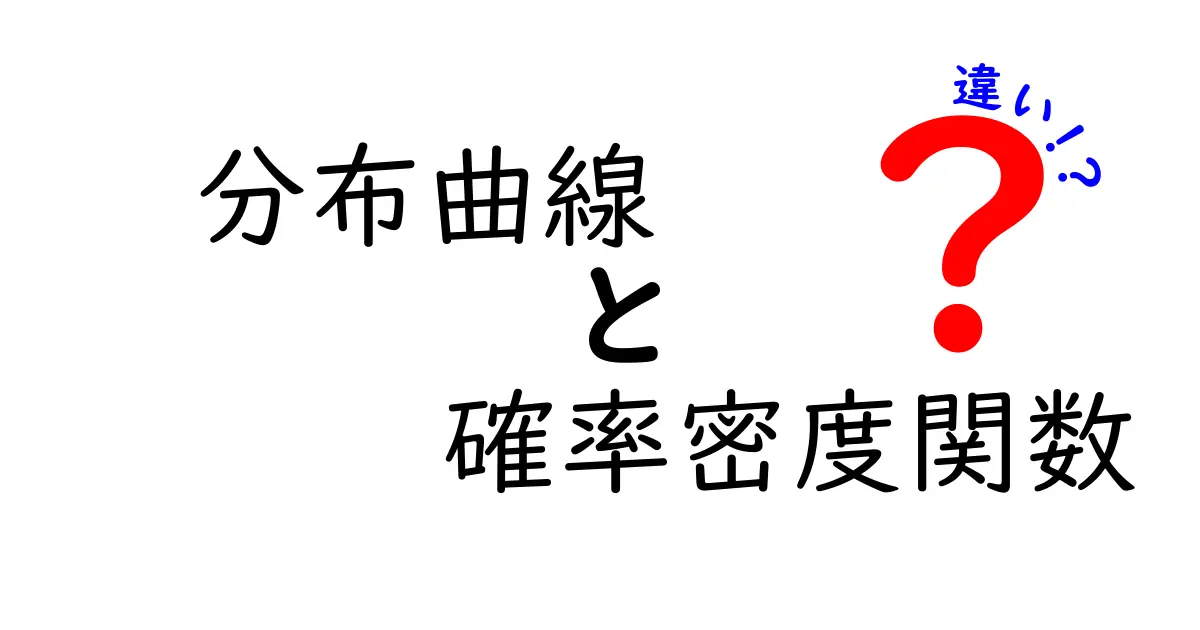
分布曲線と確率密度関数の違いを徹底解説!
皆さんは分布曲線と確率密度関数という言葉を聞いたことがありますか?これらは統計学や確率論でとても重要な概念ですが、似ているようで実は異なるものです。このブログでは、分布曲線と確率密度関数の違いを、中学生でもわかりやすく説明します。
分布曲線とは?
分布曲線とは、データの分布状況を表すためのグラフのことです。例えば、ある試験の点数がどう分布しているのかを示すために描かれる曲線が分布曲線です。ここでは、どの点数が多かったのか、または少なかったのかが一目でわかるようになっています。
確率密度関数とは?
一方、確率密度関数(けつりつみつどかんすう)は、連続確率変数の確率分布を数学的に表現したものです。具体的には、確率密度関数は、ある範囲にデータが存在する確率を求めるための関数です。分布曲線が確率密度関数のグラフであることもありますが、確率密度関数は数学的に定義された関数です。
分布曲線と確率密度関数の違い
| 特徴 | 分布曲線 | 確率密度関数 |
|---|---|---|
| 定義 | データの分布を視覚的に表現したもの | 連続確率変数の確率分布を数学的に表した関数 |
| 例 | 試験の点数の分布 | 正規分布の数式 |
| 目的 | データの様子を直感的に理解するため | 特定の範囲の確率を計算するため |
まとめ
分布曲線はデータの分布状況をグラフで表したもの、確率密度関数は確率の計算を目的とした数学的な関数です。一見似たような名前ですが、それぞれの役割は異なります。統計の学習を進める中で、これらの概念の違いをぜひ理解しておきましょう!
確率密度関数という言葉、少し難しそうに思えるかもしれませんが、実は日常生活でもよく使われる概念なんです
例えば、学校のテストの点数を考えてみてください
もし、みんなの点数が平均的に広がっていると、分布は正規分布に近くなります
このような場合、確率密度関数を使って、特定の範囲の点数がどれくらいの確率で出るかを求めることができます
これを理解しておくと、実際のデータに対するイメージを持つのが楽になりますよ!
前の記事: « モーメントと力のつり合いの違いをわかりやすく解説!
次の記事: 分布関数と確率密度関数の違いをわかりやすく解説! »