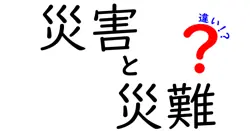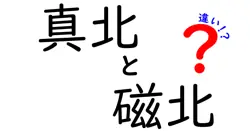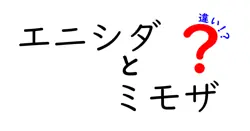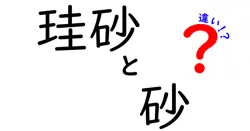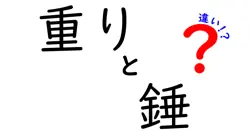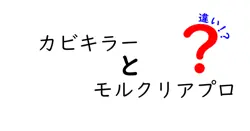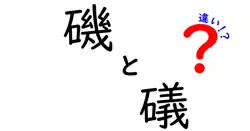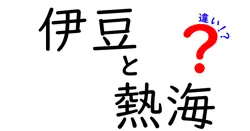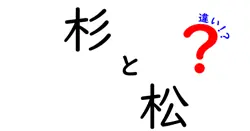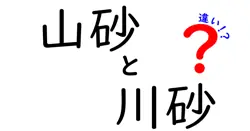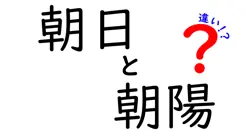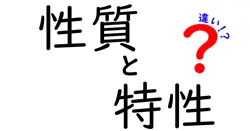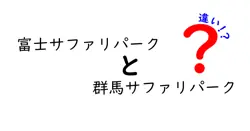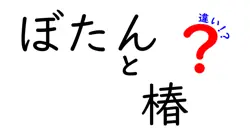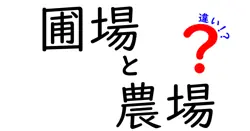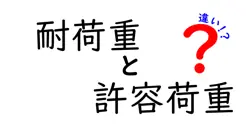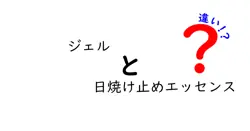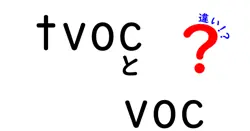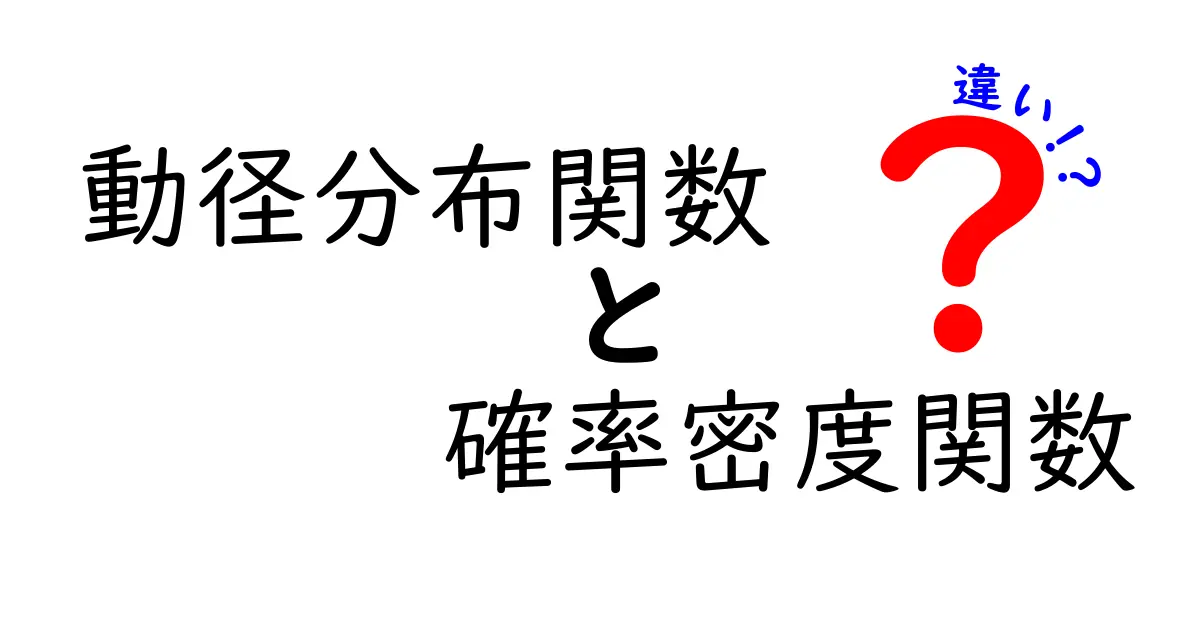
動径分布関数と確率密度関数の違いをわかりやすく解説!
私たちは日々、数多くのデータや現象に囲まれています。それを理解するためには、数学的なツールが必要になります。特に「動径分布関数」と「確率密度関数」という2つの概念は、統計学や物理学で非常に重要です。しかし、これらは似ているようで実は異なる意味を持っています。今回は、これらの違いについてわかりやすく解説します。
動径分布関数とは?
動径分布関数(どうけいぶんぷかんすう)は、主に3次元空間における粒子や物体の位置分布を表す関数です。この関数は、ある中心からの距離(動径)の分布を示します。具体的には、例えば、惑星や星の分布、あるいは細胞の位置など、全ての点の位置を中心からの距離で表したものです。
確率密度関数とは?
確率密度関数(かくりつみつどかんすう)は、連続確率変数が特定の値を取る確率を示す関数です。通常、確率密度関数はその面積が1になるように定義されます。つまり、グラフの下の領域が全体の1を表す形になっています。例えば、身長や体重など、連続的に変わるデータの分布を示す際に使われます。
動径分布関数と確率密度関数の違い
ここでは、動径分布関数と確率密度関数の違いを表にまとめてみましょう。
| 項目 | 動径分布関数 | 確率密度関数 |
|---|---|---|
| 定義 | 空間における位置の距離分布 | 連続確率変数の確率分布 |
| 用途 | 3次元空間内の物体の位置 | データの確率計算 |
| 対象 | 距離に関連する現象 | 連続なデータ |
まとめ
動径分布関数は、空間の中心からの距離に基づく位置の分布を表し、確率密度関数は連続的な確率変数における確率の分布を示します。これらの違いを理解することで、データの分析や物理現象の理解がより深まるでしょう。
動径分布関数についてちょっと違った視点から話してみたいと思います
動径分布関数は、例えば星の配置を考えるとわかりやすいですね
宇宙には数えきれない星がありますが、それらがどのように分布しているかを調べるとき、この動径分布関数が役立ちます
中心からの距離によって、どれだけの星が存在しているかを示すので、星の形成や進化に関する研究にも活用されることがあるんです
つまり、動径分布関数は宇宙の謎を解く手助けをしてくれるわけです!
前の記事: « 分布関数と確率密度関数の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 尤度関数と確率密度関数の違いを完全理解しよう! »